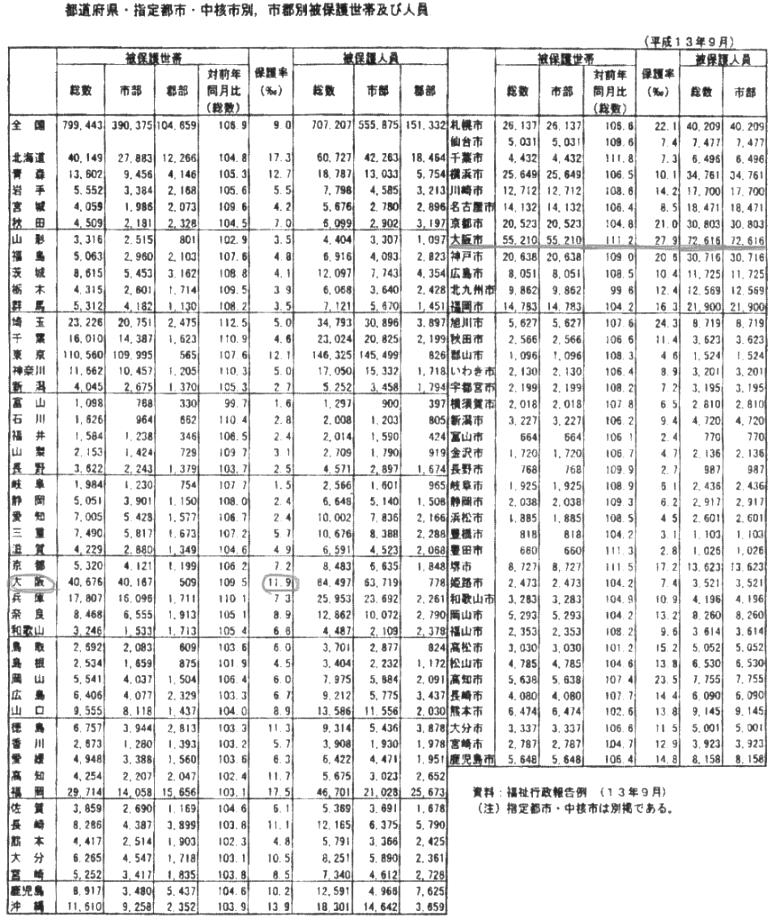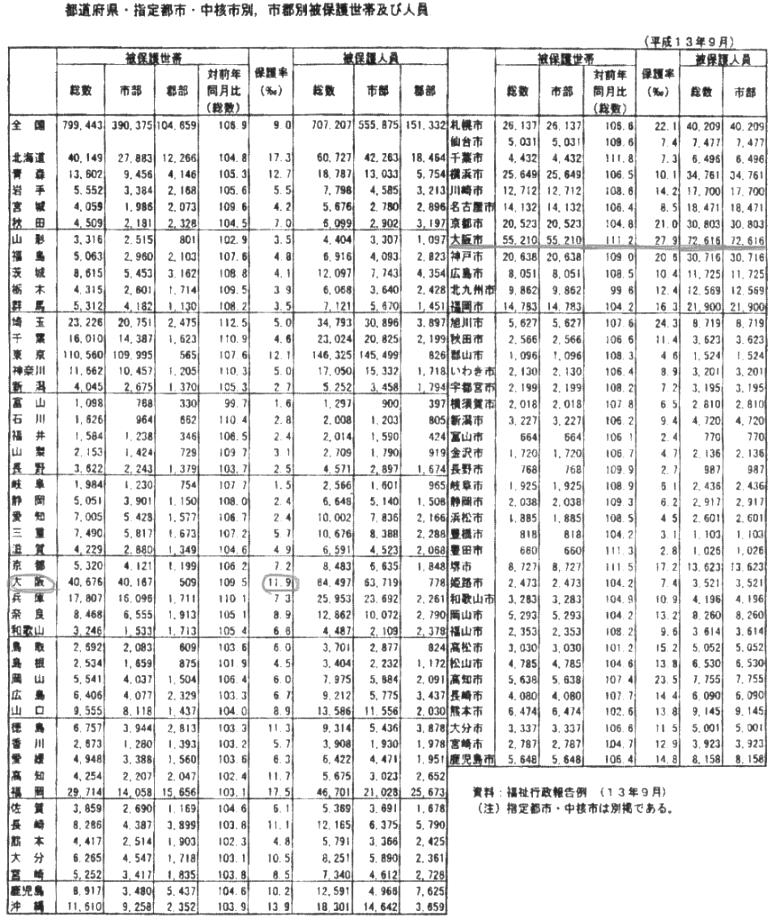������ɂ����鎩���̍s���ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s�E���J���g�������x��/����������x��
1.������̊T�v
�i�P�j�@������͒ʏ̂ōs���I�ɂ́u�������v�ƌĂ�Ă��܂��B���s������̓��k���Ɉʒu���Ă���A���ʐ�0.62�����L�����܂�̋����̒n��ł��B�����͓����̎R�J�A���l�̎��A���É��̍����ƕ��ԓ��٘J���҂������Z�ފX���`�����Ă��܂��B�l���͖�3���l�Ɛ��v����Ă���A���̂���2���l�ȏオ���٘J���҂ƌ����Ă��܂��B
�@�����̓��٘J���҂�����銘����ł́A�l�X�ȏ��ŕϗe���݂��܂��B�Ⴆ�Όٗp��ʂ��݂��60�N��͍`�p�ז�(�^�A�Ƃƌ���)�E70�N��ɂ͓S�|�A���D(�����Ƃƌ���)�E�Ƃ�킯90�N��ł͌��Ƃɏ]������J���҂��������Ă��܂��B���������̌��Ƃɂ����Ă͋@�B����I�y���[�^�[���A�u�t���[�^�v�ٗp�̔䗦�����܂���邤���A�ٗp�N�����݂�����ȂNJ�����J���҂͌ٗp����m�ۂ��邾���ł��������ɂ���܂��B
�i�Q�j�@�����������Ƃ���A�E�����߂�J���Ҏ��g�������I�ɂȂ炴��܂��A���݂�y�Ƃ����ɂ߂ē��̂����g������٘J���ɓK���ł��Ȃ�����҂�a��҂Ȃǂ͂����̘J���s�ꂩ��j�Q����A�������s���S��ɂ݂����h�����ҁs����1�t�ƂȂ��āA��茵�����������ɒu����邱�ƂɂȂ�܂��B
�s�����P�t��h�����ҁE�z�[�����X�l���̑S���I��(�P��;�l)
|
�s�s�� |
99�N3������ |
99�N10������ |
�@ |
|
���s |
8660 |
8660 |
����������1910 |
|
�����E23�� |
4300 |
5800 |
�@ |
|
�����s |
758 |
1019 |
�@ |
|
���s |
746 |
901 |
�@ |
|
���l�s |
439 |
794 |
�@ |
|
���v |
14903 |
17174 |
�@ |
|
�_�ˎs |
229 |
335 |
�@ |
|
���s�s |
200 |
300 |
�@ |
|
�����s |
174 |
269 |
�@ |
|
��t�s |
104 |
113 |
�@ |
|
�L���s |
98 |
115 |
�@ |
|
�k��B�s |
80 |
166 |
�@ |
|
���s |
53 |
111 |
�@ |
|
�D�y�s |
18 |
43 |
�@ |
|
���v |
956 |
1452 |
�@ |
|
���j23�s |
388 |
706 |
�@ |
|
���̑�74�s |
/ |
1119 |
�@ |
|
���v132�s�撬 |
16247 |
20451 |
�@ |
2.�s���@�֓��̌���
(1)�J���s��
�@�J���s���͍��s���{���̏��ǂł��芘����ɂ́A�����������E�ƈ��菊�A���{�̊O�s�@�l�ł��鐼���J�������Z���^�[������܂��B�J���҂̌ٗp�`�Ԃ͇@���ق�(�����A�J)�A���Ԍٗp(�яꋁ�l)�B���s(��ΓI���ق�)�ɑ�ʂ���܂����A���̑����͂������E���ɋ��E�o�^���A�ʏ̔��蒠�ƌĂ��u�ٗp�ی����٘J���Ҕ�ی��Ҏ蒠�v�������Ă��܂��B���́u�ٗp�ی����٘J���Ҕ�ی��Ҏ蒠�v�ɂ��O2�����ԂŒʎZ����26���ȏ�̏A�J���ؖ�������3�����ڂɊ�{13�����̎��Ǝ蓖(�A�u���蓖)�����t����܂��B�J�������Z���^�[�ł͏A�J�������Ƃ𒆐S�ɘJ���ЊQ���̂ɂ����鑊�k�E�葱����������������A���N��Ñ��k�Ȃǂ��s���Ă��܂��B
(2)������Ís��
�@�����y�҈�Ís���͎�ɑ��s�̏��ǂŐi�߂��Ă��܂��B�����ی�̎��{�@�ւł���X�����k��(�����ی�����)�s����2�t�A�����ی�@�Ɋ�Â��X���{�݂ł���X�����k���ꎞ�ی쏊�A�וێ��Ƃ��s���Ă��鐼���s���ق͌��N�����ǒ��c�̎��Ə��ł��B
�s����2�t�X�����k���ɂ�����ی쑊�k�����ƔN��ʍ\��(���s���X�����k�����Ɠ��v�W����)
|
�@ |
96/4�`97/3 |
97/4�`98/3�@ |
98/4�`99/3�@�@ |
99/4�`00/3�@ |
00/4�`01/3 |
|
���k�� |
10,422(100.0) |
17,434(100.0) |
23,961(100.0) |
27,290(100.0) |
26,293(100.0) |
|
29�Έȉ� |
67(0.64) |
69(0.40) |
74(0.31) |
42(0.15) |
65(0.25) |
|
30�`39�@ |
269(2.58) |
491(2.82) |
426(1.78) |
634(2.32) |
750(2.85) |
|
40�`49 |
1,810(17.28) |
2,962(16.99) |
3,945(14.59) |
4,177(15.31) |
4,286(16.30) |
|
50�`59 |
4,162(39.94) |
6,591(37.80) |
9,274(38.70) |
11,824(43.33) |
12,416(47.22) |
|
60�Έȏ� |
4,123(39.56) |
7,321(41.99) |
10,692(44.62) |
10,613(38.89) |
8,776(33.38) |
�@�܂��A��㎩���قɑ�\�����Љ���@�l���^�c���鐶���ی�{�݂�����̕ۈ珊������܂��B���Љ��ÃZ���^�[��100������������z�f�Ï��{�݂Ŋ�����B��̌����a�@�ł��B
(3)�x�@�s��
�@1961�N�ɋN��������1���\���ȗ�(����܂ł�23������)�x�@�ɂ�鎡����s�����傫�Ȉʒu�����߂Ă��Ă��܂��B��1���\�����_�@�ɂ��Ă��܂��܂ȍs�����W�J����Ă��܂����B1966�N6���ɑ��{�A���s�A���{�x�̎O�҂ɂ��u�O�ҋ��c��v���ݒu����܂������A���̒��S�I�Ȗ������ʂ����Ă����̂����{�x�ł����B�t�̌���������Α��{�A���s�̍s����������̕⊮�I�����ʂ����Ă����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��Ƃ����܂��B
(4)�n��^�����c��
�@��ʉƒ�⎩�c�Ƃ̕��X�ɂ�钬��Ȃǂ̑g�D�̂ق��ɁA�l�X�ȉ^���c�̂�����܂��B
�@�L���X�g���n�̂������̒c�̂͂��ꂼ��Ǝ��ɋ~�������������Ȃ��Ȃ���A�L���X�g�����F��Ƃ��Ēn��J���g���ȂǂƘA�g���ē���I�Ȑ����o���E��Ñ��k�E�N���N�n�̉z�~�����Ȃǂ����g��ł��܂��B�����̊����͊�t��J���p�Ȃǂɂ�鎩��^�c�ōs���Ă���A�s���@�ւ����g�߂Ă��Ȃ��Ƃ���ŏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂��B
�@���3����J���g���͂��ꂼ��ʂ̖��ӎ��������Ȃ���A�s�������A�J�����c�A�~�������A�J�����k�ȂǂɎ��g��ł��܂��B
3.������ɂ����鎩�������^�{��̑n��
�@������ɋN������P�g�̘J���҂ɂ��āA�Ⴆ�Ώ�ق��̈�ʘJ���҂Ƃ̔�r�Ō����A���ق��Ƃ����ٗp�`�Ԃł��邽�߈��肵��������ꂸ�A���̂��ߑ������Œ�I�ȏZ�����m�ۂ���Ă��炸�A�ߐH�Z�ɂ킽���Đ������s����ł���a�C�̏����̒i�K��y���ȃP�K�̂Ƃ��ɗ×{����ꏊ���\���������̌�����܂��B�����č�����Q�����J���҂͈�w����ƂȂ�܂��B������������ɂ��钆�őg�����̌����ȓw�͂��������Ă��܂��B���̊ԁA�]���̕����E��Â̘g�ɂƂǂ܂�Ȃ��V���ȑٓ��Ƃ���NPO�ƘA�g�����s���{�i�߂�����܂��B�s����3�t�������Ȃ��炻�̑����̎��Ƃ��s�P��E������̊����t��t���Řd���Ă��邱�Ƃ�������m�ۂ͑傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�J���҂̕�������͍s������̑���ɂ킽����̂������A���݂ɂ����Ă��s���@�֑��݂̘A�g���}���Ă��܂����A�J���E�����E��ÁE�ی������ł͂Ȃ��A�Z��Ȃǂ����ꂽ�����I�Ȏ{��ƂƂ��ɐi�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ����܂��B�s����4�t������̖�肪��������ȉۑ�𑽂�����邱�Ƃ���y�э��ɂȂ炴��Ȃ��Ƃ̈ӌ�������܂����A���̑S�Ă��s�������Ɉ�����]���́u�����W���^�{��v�̉��I�ȑΉ�����A�ł��n�̗�����������NPO�Ƃ̑��ݘA�g�Ȃǁu���������^�{��v�̑n������w���߂���ƌ����܂��B
�s����3�t
�@����ғ��ʐ��|���ƥ���啝�ȓ��ق����l�̌�������A���ɍ�����ق��J���҂��ٗp�@��邱�Ƃ�����ɂ��邱�Ƃ���A���̊m�ۂ�}��B
�A�A�n����������H���|����(1�������肨���ނ�66�l)
�C�A������٘J���ғ������J���҂ɑ��A���X600�l�̏h���������B
�s����4�t
�@���{�m���E���s���ɂ��{�s���k��ɂ����āA�������n��̂܂��Â���̎��_���܂߂��������I�Ȃ��肩����W�]�𑍍��I�Ɍ������邽�߁A�u����������ψ���v���������A98�N2���u�������n��̒������I�Ȃ�����v���܂Ƃ߂�ꂽ�B
�@���q�͇@����Ɩ��_�̍��ł́A�������E�J���҂̐����E�A�J�̏E�����̏E����J���ҁE�n����̘H�㐶���҂̏E�n��Љ�E�{�����e�B�A�c�́E�J���g���E�ƊE/���Ə��E���ɂ�����Ή����L�ڂ��A�A����̂�����ł́A�ٗp��̍���E�����̉ۑ�E���������猩���������n��̉ۑ���L�ڂ��A�B�܂Ƃ߂ł́A�c�_�̌p���Ɠ��ʗ��@�[�u�Ȃǂ̕K�v�����L�ڂ��Ă���B
4.�J���g���̎��g�݁c�����x��
(1)�����x���̎��g��
�@�x���͖��N�u�������̉��P�Ɋւ���\������v�������ɑ��čs���A�ʔN�I�ȑ�̏[���A�N���N�n��̉��P�A�����I��̊m���̂��߂̍��ւ̓��������Ȃǂ����ߎ��g��ł��܂��B���e�́Ai�@�����I�{��̊m���A��Nj@�\�̐ݒu�@�A�@�X�����k���̋@�\�[���A�n��ɊJ���ꂽ�s���@�B�@�{�ݐ����Ȃǐ����ی�s���̏[���@�C�@�s�����ɂ����鍂��ґ�A�����A�A�J�������Ƃ̎��{�@�D�@�N���N�n��̉��P�@�E�@���ւ̑�������{�̓��������A�Ȃǂł��B
�A���̒��ŁA�N���N�n�Ɓs����4�t�́A�N���N�n�̋x���ɂ���ĘJ���s�ꂪ������E���Ȃ����߂ɈߐH�Z�ɍ�������J���҂ɓ��ʑ�Ƃ��đ��k���Ƃ������Ȃ��Վ��h����(2001�N�x��12/29�`��1/7)����鎖�Ƃł��B�����E���l�E���É��E���ł����{����Ă��܂����A������̕⏕�͖������ꂼ��̊e�s�s�̒P��Ƃł��B���̎����ɐE�ɏA���Ȃ���Ζ�h��������A���~���̐����ɂ����鎖�Ƃł���A�S�s�I�ȉ����̐��Ƒg�����̏o�ɂ���đΉ����Ă��܂��B���٘J���҂̓���I�Ȑ����̈���Ƃ������{�I��肪�������Ȃ����ł́A�p�����Ď��{������Ȃ����ƂƂȂ��Ă��܂��B�x���Ƃ��Ă����Ɠ��e�̉��P�����߂�ƂƂ��ɁA���ɑ��ĕK�v�ȑ�ƈʒu�t���ĕ⏕���o���悤�Ɏ��g�݂�i�߂Ă��܂��B
�s����4�t�u�������v�N���N�n�Ə�(2001�N�x)
|
�@ |
12��29�� |
30�� |
31�� |
���v |
2000�N�x�� |
|
���k�l�� |
1,810 |
523 |
8 |
2,341 |
2,269 |
|
�������� |
1,771 |
514 |
5 |
2,290 |
2,238 |
|
���ށE�p�� |
7 |
1 |
1 |
9 |
9 |
|
���@ |
6 |
1 |
2 |
9 |
3 |
|
�{�ݓ��� |
2 |
2 |
�@ |
4 |
6 |
|
���̑� |
24 |
5 |
�@ |
29 |
13 |
|
�Վ��h���������� |
1,751 |
500 |
5 |
2,256 |
2,217 |
�B�X�����k���ɂ��ẮA������ɕ��݂��ꂽ24�̕����������ɑ���25�Ԗڂ̎��{�@�ւƈʒu�t�����A������̏Z���̂Ȃ��v�ی�҂ɑ��āA�����ی�{�݂ւ̓����������͓��@�Ƃ�������ꂽ�͈͂̂Ȃ��Ő����ی쑊�k�������Ȃ��Ă��܂��B�������Ȃ���A���������@�����ꂩ�̎�i�ŌX�̃P�[�X�ɑΉ�����ɂ͕s�[���ł���A�X�����k���̋@�\�[���A���肩���̌�������i�߂Ă��܂��B
(2)�X�����k���E��ɂ�����c�_
�@�X�����k���ł́A�s�������������ɔ��W�����o�����猟�����s���Ƃ��Ă܂Ƃ߂Ă��܂��B�ȉ��͂��̗v�_�ł��B
�@�܂��A�u���s�̕����s���A�X�����k�����������̃j�[�Y�ɉ�����Ă��Ȃ��v�u�������Ɍ��肳��Ȃ����٘J���s���z�[�����X��w�i�Ƃ����s���̌��E�v�u�s���@�ւ̗L�@�I�A�g�̌��@�v�u�Z���s��ґ�̌����v�u�X�����k���̈ʒu�t���̞B�����v������F���Ƃ��A�X�����k���̂��肩���Ƃ��āu�@�\�̖��m���v�u����{��̕n�コ�̉����v�u�ʐڑ̐��̋����v�u���������̐����v�Ȃǂ̉��P���q�ׂĂ��܂��B�����č���̉����̂��肩���Ƃ��āu�����������Ƃ̊W�̖��m���v�u�s��S�̂̏Z���s��ґ�̎��{�v�u��Ñ̐��Ƃ̘A�g�Ɛ����v�u�Z�������{�݂̊g�[�v�u������ی�̎��{�Ƃ��̂��߂̃P�[�X���[�J�[�̔z�u�v�u�A�J�������̏h���E�H���̒Ȃǂ̃T�[�r�X�̕K�v���v�Ȃǂ̉��P�Ƃ��킹�A�X�����k���̋@�\���v�Ȃǂ̐�������Ă��܂��B
�@���̒ŏo����Ă��錻��F���≇���̍���̂�����ł́A������ɂƂǂ܂�Ȃ��ۑ�ƂȂ��Ă����h�����҉ۑ�Ƃ��A�����A�x���Ƃ��Ă̎��g�݂�i�߂邤���Ŏ�����^������̂ƌ����܂��B
(3)�����J�̎��g��
�@�����J�́A��s�s������������̒��ɁA������̂悤�ȁu�J���҂̊X�v������A�����E���l�E���É��E������Ɋe�s�s�̖����x���Łu�J���҂̊X�A����c�v���������A���N�ΐ��{�v�����o�������J���Ȍ������g��ł��܂��B��Ȍ����ڂ́A�@�@�u�J���҂̊X�v�ɂƂǂ܂�Ȃ���h�����Җ��ɂ��č��Ƃ��Ă̑Ή��@�A�@�����s���̐��i�̂��߂̐�Nj@�\�̐ݒu�A�@�B�@���ʏA�J��̎��{�A�@�C�@�����ی�{�݁A��Ë����̐��̐����A�@�D�@�����̂��Ǝ��ɍs���Ă��鎖�Ƃւ̏����Ȃǂł��B���������́A�Ƃ�킯�ً}�̉ۑ�ƂȂ��Ă����h�����҂ɂ�������Ă�99�N5���Ƃ�܂Ƃ߂́w���ʂ̑Ή���x�Ɏ���������z���邱�ƂȂ��A�܂��u�J���҂̊X�v�̖��͎����̌ŗL�̖��ł���Ƃ̗�����Ƃ��Ă���A����Ɍʂ̗v���ɑ��Ă͊���̐����ی�s���͈͓̔��ł���ΑΉ�����Ƃ̉ɏI�n���Ă��܂��B
5.�@�����肪�s���I�ɒ��ڂ��ꂾ��40�N���o���܂����B�܂��A�^���c�̂��s���������͂��߂Ă���20�N�ȏオ�o�߂��A������̊O�ς͑傫���ς���Ă��܂����B
�@�������Ȃ���A���̖{���͕ω����Ă��炸�A�s�����D�����s���̃T�C�N���̒��Ŗ|�M�����J���҂̎p�͂��̂܂c��A���܂�����̔g���e�͂Ȃ�������ɉ����Ă��܂��B
�@�x���̂���܂ł̊�����s���ɂ��Ă̎������^���̕s�[�����ɂ��Ĕ��Ȃ��A�����������̘J���҂��s���̂�����ɐ^���Ɍ����������Ȃ���Ύ��Ԃ͐i�s���Ȃ����Ƃ�N���ɒu���w�͂��s�������ƍl���Ă��܂��B
�U�D�����敟���������̌���Ɖۑ襥�����������x��
�@������̉��v�y�ё��s�Ƃ��Ă̑Ή��ɂ��ẮA�s�E�����x��������Ă���܂��̂ŁA���x������͐����敟���������̌���Ɖۑ�ɂ��ĕ��܂��B�܂��A���N�̃��|�[�g�ł��T���͂��łɕ��Ă���܂��̂ŁA�ŋ߂̓����I�ȓ_�ɍi���Ă܂Ƃ߂����Ă��������܂����B
(1)���������鐶���ی�P�[�X
�@�����敟���������ŏ��ǂ��鐶���ی�̔�ی쐢�ѐ���2002�N3�������݂�15081�P�[�X�B(�����敟���������W�v)�@2001�N3�����̔�ی쐢�ѐ���13032�P�[�X(�����W�v)���������Ƃ���A����2000�P�[�X���܂肪1�N�Ԃɑ������Ă��邱�ƂɂȂ�B���̑唼�͒P�g����тł���B���Ȃ݂�5�N�O��1997�N3�����̔�ی쐢�ѐ���7543(�����W�v)�P�[�X�ł������B���Ȃ킿5�N�ԂŔ{�����Ă���킯�ł���B�������������������X���́A�����܂ł��Ȃ��������s��������������Ă��邱�Ƃ��傫�ȗv���Ɖ�����邪�A������̘J���҂ւ̕s���̒����́A���l�ɘJ���҂��h������ȈՏh�����ւ��傫�ȉe�����y�ڂ����B���̉e���ɂ��98�N�������(���m�ɂ͂���ȑO�ɂ����邪)�A�ȈՏh�������A������u���ىc�Ɓv����u�A�p�[�g�o�c�v�ɕύX����Ă����悤�ɂȂ����A���̐���4�N���܂��30�������B�A�p�[�g������������������Ƃ�������e���͂Ȃ��悤�Ɏv���邪�A����30�����܂肪�ۗL���镔���~�͂Ȃ��2600�`2700���ɒB����B������̂��ׂĂ������ی�҂ł͂Ȃ����A�`���ɋL������ی쐢�т̋}���ȑ������x����Љ���Ƃ��ĎM�̖������ʂ����Ă���Ƃ�����B���̊ȈՏh�����̃A�p�[�g���̓����͍�����������̂ƍl������B���������āA�M�̃L���p�V�e�B�������邱�Ƃɂ��A����ɐ����ی�P�[�X���͑����̈�r�����ǂ邱�ƂƂȂ邱�Ƃ���s���Ƃ��ėL���ȑΉ������߂��Ă���B
�@����A��h�����ґ�Ƃ��Đ�������ɂ������x���Z���^�[���ݒu����A���݈ꎞ���ɂ��Ă��ݒu����Ă����Ƃ���ł��邪�A������̏��ۑ�̉����Ɍ����Ē���������ʂ������炷�ɂ͎����Ă��Ȃ��B���{�E�s�̍s���{��͘J���E�����E��ÂȂǂ̕���ň��s���Ă�����̂́A����ɑΉ���������ʓI�ȑu�����Ă��Ȃ��̂������ł���B
(2)���s�s�Ƃ̔�r
�@������ɂ����鐶���ی�s���A�Ƃ�킯�����敟���������̑傫�ȉۑ�Ƃ��ăP�[�X���̋}���̏��q�ׂ����A��������������K�͉����Ă��邱�Ƃ��傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B�P��̕�����������15000�]�̃P�[�X�����ǂ��邱�Ƃ͑g�D�̋@�\�̖ʂ�������E�������Ă��Ă���Ƃ��킴��Ȃ��B2002�N�x�̐����敟���������̎��s�̐��́A�ے����̕������������ȉ��A���@�w�����A�P�[�X���[�J�[���A�����E�����܂�195���őΉ����Ă������ƂƂȂ��Ă��邪�A��剻���������������̉^�c�́A�����ی�s�������s���Ă��������ŗl�X�ȓ_�Ŏx������������ƂƂȂ��Ă��Ă���B�����������̋K�͂͂ǂ̒��x���K�Ȃ̂��A�c�_������Ƃ���ƍl���邪�A�Q�l�ɓs���{���E���ߎw��s�s�E���j�s�ʁA��ی쐢�ѐ��y�є�ی�l���̈ꗗ(2001�N9������)�������Ƃ��ĎQ�Ɗ肢�����B���̈ꗗ�\�ł͕����������̐ݒu����������Ă��Ȃ��̂ŁA��r����ɂ͕s�\���ł��邪�A15000�Ƃ����������ǂ̒��x�̋K�͂Ȃ̂��͗e�Ղɐ��@�ł���Ǝv����B
�@������ɂ��Ă�����ɑΉ��ł���̐��Ƃ��Ă������߂ɕ����������̐ݒu�̂�������܂߂����{�I�Ȏ��{�̐��̌������������Ă��邱�Ƃ͖����ł���B
(3)�����敟���������u�����v�̐ݒu
�@�ȏ�̂悤�Ȕ�剻���������������̖����ꕔ�ł��������Ă������߂ɁA2002�N�x��萼���敟���������Ɂu�����v���ݒu����邱�ƂƂȂ����B�u�����v�ɂ�����Ɩ����e���ɂ��ẮA�J�g�Ō����ψ����ݒu���A�c�_�������Ȃ��Ă����B��̐����敟���������̎��{�̐��̐l���́A���́u�����v�̐l�����܂߂����l�ł���B����ł́u�����v�ݒu�ɑ��鐥��̋c�_���������Ƃ���ł��邪�A��K�͕����������̖�������ێ��̑̐��ł́A��������̕����Ɍ�����Ȃ����ƁA���{�I�Ȏ��{�̐��̕ύX��P�N�x�ōs�����Ƃ͍���ł��邱�ƂȂǂ���A���㐼����S�̂̕����s���̂�������������Ă������߂̈���Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă����Ƃ���ł���B
�@�����敟���s���̖��Ɖۑ�́A���ʂƂ��ăP�[�X���̋}�������ۂƂ��ĕ\��Ă��Ă��邪�A��������ɋN������v�f���傫���A�t���Đn�I�ȑ�ł͔��{�I�ȉ����ɂȂ���Ȃ��B�u���������̂ɓ����Ȃ��A�����Ƃ��낪�Ȃ��v�Ƃ����i���ɏے������悤�ɁA�u�A�J�{���@���ɓW�J����̂��v�Ƃ�����ւ̓����Ȃ���A�K�R�I�ɁA�����{��ł̑Ή����]�V�Ȃ�����A���ʓI�ɉߓx�ȕ��S�������̗̈�ɂ̂�������A�{���A�Œᐶ����ۏႷ�邽�߂Ɉʒu�Â����Ă��鐶���ی쐧�x�����ԂƂ��ċ@�\���Ȃ��Ȃ鎖�Ԃ��������ƂƂȂ�B
�@�����ی�@�����̖{�|�̂Ƃ���@�\���邽�߂ɂ́A�����ی�ɂ�����܂ł̉ߒ��ŁA�l�����퐶�����c��ł��������ł̎Љ�I�����Ƃ��ẮA�J���E�Z��ȂǂƂ������Љ�K�v�s���ł���B���������Љ���̐����́A�s���̎傽��Ӗ��ƍl����Ƃ���ł���A�W����s���@�ւ̓��ݍ��Ή������߂����B