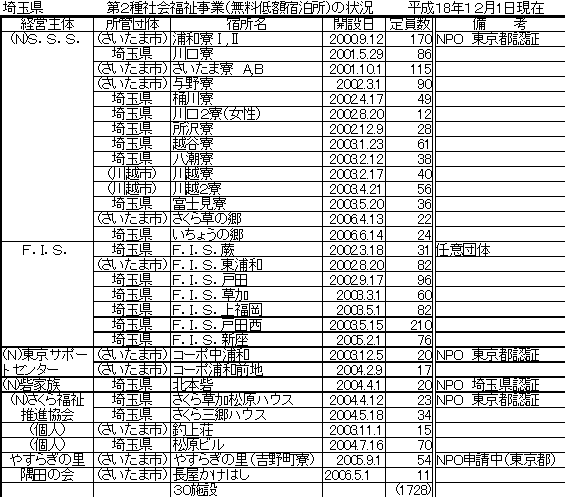 �@
�@
��ʌ�
��ʌ��z�[�����X�x���v�搄�i�ψ���
http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BB00/homeless/suisinkaigi.html
�Љ���W�ҁ@���Y�M���@��ʌ��Љ�����c���@�@�ψ���
�w���o���ҁ@�@�@�{���R���@�Y�a��w���������w����C�u�t�@��ƕ���
�x�������W�ҁ@�g�i���q�@�������܃z�[�����X�T�|�[�g
�ٗp��W�ҁ@�͌��ː^�@��ʌ��ٗp�c��A�J�A�h�o�C�U�[
�s�����E���@�@�@���������@�˓c�s�����������ے��@�@�@�@�@���ψ���
�s�����E���@�@�@��c��s�@����s�����������ۉے��⍲
�i�����P�W�N�R���R�P���܂Łj
�z�[�����X�x�����_�i�L��I�E���I�x�������̓W�J�j�ɂ���
�`�����P�V�N�x�@�z�[�����X�x���v�搄�i�ψ����ƕ���@�����P�W�N�R��
�P�@���ꂩ�猩����ʌ��̃z�[�����X�̌���
�i�P�j���a�E��Q��������l�������A���Â���]���Ă���҂������B����������ŕa�@�֍s�����Ƃ�i�����Ă��A�g�Ȃ肪�����Ȃǂ̗��R����I�@�ւɑ��鉓�����狑�ۂ���P�[�X���ڗ��B���̂��ߌ��N��Ԃ������܂ܘH��Ő������Ă���l��A���������Ă���~�}�ԂŔ��������P�[�X��������B
�i�Q�j���j�₻�̑������ǂ��^����P�[�X������A���Y�{�l�̌��N���݂̂Ȃ炸�A���ӏZ���ւ̊��������O�����B
�i�R�j�ʍs�l�Ȃǂɂ��z�[�����X�ɑ��錙���点��\�́A�����Ƃ��Ă���Ԃւ̕��Ȃǂ��������Ă���B
�i�S�j�킸���Ȃ���ł����Ă��A�J�����Ă���l�������B�⑫�I�E�����I�Ȏx��������A�H�㐶����E�o�ł���\�������l���܂܂�Ă���B�܂��A�N��A�Z���A�ۏؐl�A�Z�\�Ȃǂ���ǂƂȂ�A�E���Ȃǂ�����d���ɏA�����Ƃ͎����㍢��ł���B
�i�T�j����ł̓z�[�����X�ɂƂ��āA���p�ł���Љ���͐����ی�Ɩ�����z�h�������p�̓�����I�������Ȃ��A���ǁA�H�㐶�����p������Ă��܂��B
�Q�@�z�[�����X�x���{��̌���Ɖۑ�
�i�P�j������z�h����
�@�����̃z�[�����X�x���́A�����ی�����p���A������z�h�����i�Q�V�J���A����P�C�U�S�U�l�j�ɓ�����������ŁA���d�����̐����ۑ���������A�A�J�x�������s�����Ƃɂ��A������}�邱�Ƃ����S�ƂȂ��Ă���B
������z�h�����̓����҂ɂ́A����ҁA��Q�ҁA���a�ҁA�c�u�̏����ȂǁA���l�Ȑl���܂܂�Ă���B�ꕔ�ɂ́A����җp���A���ɓ��������h�������ݒu�����悤�ɂȂ������A�n�[�h�I�ɂ��\�t�g�I�ɂ��A�l�X�ȃj�[�Y�ɑΉ��ł���̐��ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�]���āA���p�҂̒��ɂ͏����ł��Ȃ��P�[�X�������Ă���B
�i�Q�j�H�㓙�̃z�[�����X�ɑ���x��
�@�H���͐�~���ɋN������z�[�����X�i�����P�V�N�W�����݁A�W�O�W�l�j��ΏۂƂ���{��́A���k���ɂ�鏄�k���Ƃ����S�ł���B�������A���̊������e�͈��ۊm�F����ł���A�e��̐����ۑ�ɑΉ������x����i���s�����Ă���B
�i�R�j�����ی�ɂ��Ή��̌��E
�@�z�[�����X�ɑ���x������́A������A�����ی쐧�x���B�ꂩ�Ō�̎�i�ƂȂ��Ă���B�������Œᐶ����ȏ�̏A�J������N�����̎���������z�[�����X��A�J�\�͂�L���A�����ꂪ����Ȃ�����A�J���Ȃ��z�[�����X�͐����ی�̑ΏۂɂȂ�Ȃ��B�܂����ۂɂ͗v�ی��Ԃɂ����Ă��A�s���Ƃ̂���܂ł̊ւ�肪�K�������ǍD�łȂ��l������ɕ~���̍����������Ă���l�́A�����ی�̐\�������߂炤�ꍇ�������A�ŏI�I�ɂ͘H�㐶���̒������ɂ���Č��N��Ԃ��������A�����̊�@�ɂ��炳���ꍇ������B
�@�܂������ی�̑ΏۂƂȂ����Ƃ��Ă��A���ۂɏZ�ރA�p�[�g��T������A�A�p�[�g�ɓ���������̂��ߍׂ��Ȑ����x������S�Đ����ی�őΉ����邱�Ƃ͋ɂ߂č���ł���B
�@���̂悤�ɐ����ی쐧�x�Ɉˑ������z�[�����X�x���́A�K���������ׂẴz�[�����X���̉����ɑ��Č��ʓI�ł͂Ȃ��A����Ɋe�����̂ɂƂ��Ă��A�z�[�����X�x���̑̐����K�������\���ɐ����Ă��Ȃ����߁A��������₷���Ȃ��Ă���B
�i�S�j���̐��x���p�̌��E
�@���̐��x���A�z�[�����X�����p����ɂ́A�����ی�ȏ�ɓ���Ƃ�����B�Ⴆ�A�z�[�����X�̒��ɂ́A�N���̎�������l�������������@�@�Љ�A�ł���l�����邪�A�N���̎\���⎩�Ȕj�Y���̎葱�������邽�߂̏Z�����ݒ�ł��Ȃ����̖�肪����B
�i�T�j�\����`�̖��
�@�����ی���܂߂āA������̐��x���A�{�l�̐\���������Ă���A���k���n�܂�B�{�l�����x���̂��̂�\��������m��Ȃ��ꍇ��\�������ɍs�����Ƃɏ��ɓI�ȏꍇ�ɂ́A�Ή��ł����A�܂��܂���������������Ƃ�����肪����B
�R�@���Ԏx�������̌���Ɖۑ�
�i�P�j�x���c�̂̌���
�@�����̃z�[�����X�x����ړI�Ƃ���NPO���̎x���c�̂́A�����ɂS�`�T�c�̂ł���A����ɂ�鑊�k������_��Ƃɂ�鎩���x�����A���F���銈����W�J���Ă���B�c�̂̒n���Ȋ����ɂ���āA�z�[�����X�Ƃ̐M���W���\�z����A���݂ł̓A�p�[�g�����A�A�E�A���N�̉Ȃǂ̐��ʂ�������悤�ɂȂ����B
�i�Q�j�}���p���[�s��
�@�������A������̒c�̂����K�͂ł���A�p���I�Ɋւ���Ă���x���҂͂P�O�l�O��ł���B�����āA��ÁA�ی��A�Љ���A�Љ�ی��A���d���A�J���A�Z�����̐��E���s�����Ă���A�܂��o�b�N�A�b�v����@�ւ��Ȃ��A���I�ȑ��k�ւ̑Ή���������߁A��肪���u����Ă��܂��P�[�X������B
�i�R�j�c�̊Ԃ̘A�g�̕s�\����
�@���������ۑ���������邽�߂ɁA�c�̊Ԃ̘A�g���s���ł���Ƃ����F�������܂�A���݁A�c�̂ɂ�����I�ȘA������J�Â��A�����������s�����A�������k���f�������͂��Ď��{����悤�ɂȂ��Ă���B
�@���̂悤�ȋ@���ʂ��āA�e�c�̂̓������含����������邱�Ƃɂ���āA�Ⴆ�A����z�[�����X�̎��a�̔����ƕa�@�ł̎��Â��x�����A���̌��ʁA�H�㐶���̒E�o�̌��ʂ��������P�[�X���������B�܂��z�[�����X�x���c�̈ȊO�̒c�̂Ƃ̘A�g���\�z�������A���_�����̂���z�[�����X�ɑ��Đ��I�x�����J�n�ł����P�[�X������B
�@�����������_�ł́A�e�c�̊Ԃ̃R�[�f�B�l�[�g�����s�݂ł���A����I�Ȓc�̊Ԃ̘A�g�ƃV�X�e�������ꂽ�x���̐����\�z����Ă��Ȃ��Ƃ����ł���B
�S�@�z�[�����X�x�����_�̕K�v��
�@�z�[�����X���̉����́A�X�̃z�[�����X�̎����͂������A�n��Z�������S���ĕ�炵�Ă������߂ɂ��d�v�ł���B�]���āA��L�̉ۑ������ɓ��ꂽ�x���̐����K�v�ł���B
�@�z�[�����X�x���̎������K�������\���łȂ���ʌ��ɂ����ẮA�����̎��������ʓI�Ɋ��p���邽�߂ɂ��A�s���Ɩ��Ԃ̊e����̊W�@�ցE�c�̂����ڂȘA�g��}��A�����I�Ȏx�����s���K�v������B
�@�܂��A�e�n��ɖ��������p���I�Ȏx�����x�[�X�Ƃ��Ȃ�����A������o�b�N�A�b�v����L��I���I�Ȏx�����K�v�ł���B
�@�܂�A�e����̉��̘A�g���[��������i�������j�ƂƂ��ɁA�e�x���@�ւ̃o�b�N�A�b�v��}��A�x���̑w����������i���w���j���Ƃ����߂���B�������������I���w�I�x���̐����\�z���钆�j�Ƃ��āA�x�����_���K�v�ɂȂ�B
�@�@�y�����P�z�A�y�����Q�z
�T�@�x�����_�ɋ��߂���@�\�@�y�����R�z
�i�P�j�����W
�E�z�[�����X�Ɋւ�������W�A����
�@�z�[�����X�̎��Ԃ���ۑ�A�x���j�[�Y����c������B
�E�z�[�����X�̎x���Ɋւ���Љ���̏����W
�@���p�ł���Љ���i�ꏊ�A���x�A�x�����e���j��c������B
�i�Q�j�x������
�E�x�����K�v�ȃz�[�����X�ɑ��āA���̏ꏊ��j�[�Y�܂��āA�K�ȎЉ�������n������B
�E�x���������s���Ă���e�c�̂�@�ւ̋��߂ɉ����āA�����A��ÁA�@�����̐��I���n����A�l�I�R�[�f�B�l�[�g���s���B
�i�R�j���y�[��
�E�n��Z����e��c�̂�ΏۂɁA�z�[�����X�̎��Ԃ�z�[�����X�x���Ɋւ��闝����[�߂邽�߁A���y�[���������s���B
�i�S�j�l�b�g���[�N����
�E�z�[�����X�x���Ɋւ���Љ�����J��ƂƂ��ɁA�Љ�����݂̋��́A�A�g���ł���̐����\�z����B
�i�T�j�Љ�A�ւ̃X�e�b�v
�E���x�⎑���𗘗p���邽�߂̑O������𐮂��A�Љ�A�ւ̑�������ƂȂ�x�����s���B
�@���q����Ԃ̉��P�A�Љ�W�̌`���A�A����@�\�̒Ȃ�
�U�@�x�����_�̉^�c���
�_��A���l���A�l�b�g���[�N���ɕx�݁A�z�[�����X�x���Ɏ��т̂���m�o�n���̖��Ԏx���c�̂ɂ��^�c���]�܂����B
�@�@�@�k���R�l�@�z�[�����X�̑��l���ً}�̉ۑ�ɑΉ����邽�߁B
�@�@�@ �@�@�@�@�A�s���ɑ���畏�������z�[�����X���ɑΉ����邽�߁B
�@�܂��A�^�c��̂ƂȂ閯�Ԏx���c�݂̂̂ɔC����̂ł͂Ȃ��A�s����l�X�ȕ���̎x���@�ցE�c�̂��g�D�I�A�l�I�Ɏx����d�g�݂ɂ���K�v������B
�@�Ⴆ�A���N�x�ANPO�����I�Ɏ��{�����u�������k��v�̂悤�Ȏ��Ƃ��A����s�����̎��ƂƂ��Ĉʒu�Â��A���̉^�c�̈ꕔ�Ԏx���c�̂Ɉϑ�����Ȃǂ̕��@���l������B
�V�@����Ȃ�ۑ�
�i�P�j�x�����_�̋�̈�
�@���i�K�ł́A�x�����_�̎�Ȗ����́A�z�[�����X�x���c�̂̃o�b�N�A�b�v�ł���A�܂��`�ԂƂ��ẮA�����^��ʏ��^�ł͂Ȃ��A�E�������n��K�₵�Ďx���������s���A�E�g���[�`�^���\�z���Ă���B�x�����_�ɂ́A�ŏ����A�E��2�����x�Ǝ����X�y�[�X���K�v�Ǝv����B
�@�������x�����_�̋�̓I�ȏꏊ�A�ݔ��A�^�c�̒��S�ƂȂ閯�Ԏx���c�̂ɂ��ẮA�����_�ł͖ڏ��������Ă��炸�A����Ɍ�������K�v������B�x�����_��S�����Ԏx���c�̂ɂ��ẮA�琬�Ƃ������_����������ϋɓI�Ɋւ���Ă����K�v������B
�i�Q�j�������S
�@�x�����_�ƍs���@�ւƂ̖������S�⌧�Ǝs�����Ƃ̊W���ɂ��ẮA����ɏڍׂɌ�������K�v������B�x�����_���z�[�����X�x���̑S�Ă�S�����̂ł͂Ȃ��A�e���x�̐��I�^�p�͕������������n�߂Ƃ��邻�ꂼ��̍s���@�ւɂ����Ċm���Ɏ��{����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�i�R�j�����̖@�߂�x���Ƃ̊W
�@�u�A����@�\�v���A�����̖@�߂�l���̎�舵�����̉ۑ肪�l�����邱�Ƃ���A����Ɍ�������K�v������B
�i�S�j�n��Z���Ƃ��a�
�@�����I�ɁA�x�����_���ݒu�^�c�����ƁA�u�n��̃C���[�W���ቺ����v�u�z�[�����X���W�܂��Ă��܂��v�Ƃ������n��Z���̕s�����\�z�����B
�@���̂��Ƃɂ��ẮA���̂悤�Ȃ��Ƃ��痝�������߂Ă����B
�@�x�����_�́A�z�[�����X�̒ʏ��E�����̎{�݂ł͂Ȃ��A�x�����_�̐E�����A�E�g���[�`���s�Ȃ����Ƃ�����̎x�������̃o�b�N�A�b�v�@�\����ł��邱�ƁB
�A�z�[�����X�̏�Ԃ̈ێ��ł͂Ȃ��A�H�㐶���̏�Ԃ���E�o���A�Љ�A��ڎw�����̂ł��邱�ƁB
�B�����ǂ̖h�~��h�ƂƂ����ϓ_������n��ɍv�����邱�ƁB
�C�z�[�����X�ɑ���Ό��◝���̕s�\�������琶�������ɑ���[�����s���A�z�[�����X�ɑ��鎖���𖢑R�ɖh�����̂ł��邱�ƁB
�W�@�������@
�@��L�̉ۑ�ɂ��āA����̌��������ł͌��E������B���Ԃƍs���̋����ɂ��A�\�ȂƂ��납�玎�s�I�Ɏ��Ƃ����{���āA����i�߂Ă����ׂ��ł���B
�@�܂��A���i�ψ���ɂ��ẮA���N�x�ȍ~���p�����A�z�[�����X�x���v��̐i�s�Ǘ���}�钆�ŁA���̎x�����_�ɂ��āA����Ɍ������Ă����K�v��
��Q�� ��Q�́@��ʌ����s�������ƘA�g���čs���z�[�����X��
�i�����P�V�N�x�̎�Ȏ��Ƃ̐i���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���́A�����P�V�N�x�V�K�̎�g
�@�@�@���@�@�@�� �@���@�@�{�@�@��@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�P�@�A�Ƌ@��̊m��
�i�P�j�E�Ƒ��k���ɂ��A�J�w��
�E�Ƒ��k�����Ɓ@�����P�V�N�S���`�P�W�N�Q��������
�E�Ƒ��k���@�Q�l�z�u�A�A�J�ҁ@�S�R�l
�i�Q�j�E�ƌP���̋@��� �i�h�����E�����C��ŏ��j
�i�R�j�X�̎���ɍ��킹�����k�E�A�h�o�C�X �i�h�����E�����C��ŏ��j
�i�S�j�A�E�x���Z�~�i�[�̎��{ �@�@�@�@�i�h�����E�����C��ŏ��j
�i�T�j�E�ƏЉ�Ƃ̐��i �i�h�����E�����C��ŏ��j
�i�U�j�A�E���̎��W�E�� �i�h�����E�����C��ŏ��j
�Q�@���肵�����Z�̏ꏊ�̊m��
�i�P�j�h�����̊��p �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����P�V�N�W�����݁@�Q�T�{�݁A�����҂P�C�S�Q�S�l
���h�����E�����C��̎��{
�@�@�����P�V�N�V���y�тP�P���@�Q���҉��ׂU�Q�l
�@�@���e�F�����ی�A�A�J�x���{��A�����Ǒ���
�E������z�h�����ɑ��錟���̎��{
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���n�����F�S�P�V�{��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʌ����i�o�����j�F�S�^�c��̂T�c��
�i�Q�j���c�Z��̊��p
�i�R�j���ԏZ��̊��p
�R�@�ی��y�ш�Â̊m��
�i�P�j���N���k�E�ی��w�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�i�Q�j���j�\�h��
�i�R�j�W�@�ւƂ̋��͑̐�
�i�ی���Õ������ǑƘA�g���ďh�����E�����C����@���s�����j
�S�@�����Ɋւ��鑊�k�y�юw���̐��̊m��
�i�P�j���k��
�����P�V�N�S���`�P�W�N�P��������
�@�@�@�@�@�@�@�@����s�A�˓c�s�ɂ��ꂼ��Q���̏��k����z�u
�@�@�@�@�@�@�@�ʐڌ����@�V�T�X���A�����@�E�����Q�Q��
�i�Q�j�Ζ���ď���̎��{
�����P�V�N�P�Q���`�P�W�N�P���@�R�R�s�Ŏ��{
�@�@�@�@�S�T�U�l���m�F�@���A�T�l�������i�h�����A�{��V�l�z�[���j
�i�R�j�@�����k
�����P�V�N�S���`�P�W�N�R���@�@�@�P�R����{�@�R�V�l�̑��k�ɑΉ�
�i�S�j���k�̐��̐���
���z�[�����X�������k��i���⏕���Ɓj
�@�@�����P�V�N�P�O���A�P�Q���@�Q���ҁi���ׁj�z�[�����X�R�O�l�A�{�����e�B�A�V�T�l
�T�@�z�[�����X�����x������
�@ ���z�[�����X�x���v�搄�i�ψ����ƕ���ɂ����āA�z�[�����X�x�����_�̌������s�����@�����P�V�N�U���`�A�S��
�U�@�n��ɂ�������S�̊m��
�i�P�j�p�g���[�������̋���
�i�Q�j�Ĕ��h�~�����̐��i
�i�R�j�K�ȕی슈���̐��i
�V�@���Ԓc�̂Ƃ̘A�g
�i�P�j�m�o�n�Ȃǖ��Ԓc�̂ւ̎x�� ���z�[�����X�x���c�́i�ҁj�A����c�̊J��
���Ԓc�̑��݂̏����������s�����B�����P�V�N�T���`�A�V��
�i�Q�j���� ���z�[�����X�x���z�[���y�[�W���J��
�@�����P�V�N�V���`
�i�R�j�[������ ���z�[�����X�Ɋւ���f��E�u����i���⏕���Ɓj
�@�����P�V�N�P�O���@�Q���ҁF�����ψ���
����Љ�����Ɓi������z�h�����j�̓͏o�̎��������y�щ^�c�Ɋւ���K�C�h���C��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʌ��������Љ����
�@�H�㐶���҂�A�ЁA�����ނ����ɂ��Z��ɍ����Ă��鐶�v����҂ɑ��āA�Љ� �����@��Q���R����W���̋K��Ɋ�Â��A�������͒�z�ȗ����ŗ��p�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����h�������̓͏o�̎��������̕��@�y�щ^�c�ɂ��āA�ȉ��̂Ƃ����߂���� �Ƃ���B
�P�@�J�ݒn�̎s�������Ƃ̎��O���c
�@�J�݊�]�҂́A�{�݊J�ݒn�����ǂ���s�����A�������ی������Z���^�[�i�ȉ��u�s �@�������v�Ƃ����j�Ǝ{�݂̊J�ݑO�Ɏ{�݉^�c����ی쓙�Ɋւ��鋦�c���s�����ƁB
�Q�@�Z��������
�@�J�݊�]�҂́A�s�������Ƌ��c���A�{�݂̊J�ݑO�ɒn��Z���ɑ����������s���A �@������悤�ɓw�߂邱�ƁB������̌��ʂ́A���y�юs�������ɕ����ɂ���o���邱�ƁB�܂��A�n��Z������̈ӌ���v�]���ɑ��ẮA�S���҂��ߐ����ɑΉ����邱�ƁB
�R�@���Ƃ̎��O���c
�@�J�݊�]�҂́A�s�������Ƃ̋��c�y�яZ�������I����A���Ƌ��c���s���A�J�ݓ��͌����Ƃ��Č��Ƃ̋��c�I����Ƃ��邱�ƁB
�S�@�W�@�߂̏���
�i�P�j�J�݊�]�҂́A�J����@�E���h�@�E�H�i�q���@�E���z��@�ȂǁA�e��@�߂����炷�邱�ƁB�J�ݑO�ɂ́A�{�݊J�ݏꏊ�����ǂ���J����ē��E���h���E�ی����E���y�����������E�s�������ɂ����ĊW������葱�����ɂ��ĕK�v�Ȏw�����邱�ƁB
�i�Q�j������邢�͖ʐςȂǂ̋K�͂ɂ��e��@�߂̋K�肪�K�p����Ȃ��{�݂ł����Ă��A�@�̎�|�Ɋ�Â����^�c�ɓw�߂邱�ƁB
�T�@�@����Љ�����ƊJ�n�͓�
�i�P�j�Љ���@��U�X���P���ɂ��A�J�n������P�����ȓ��ɁA���̎�����͂��o�邱�ƁB�܂��A�����Q���ɂ��A�͏o�̎����ɕύX���������ꍇ�A�ύX������P�����ȓ��ɓ͂��o�邱�ƁB���Ƃ�p�~�����ꍇ���A���l�Ƃ���B
�@�@�A�@���ƌo�c�҂̖��̋y�ю傽�鎖�����̏��ݒn
�@�@�C�@���Ƃ̎�ދy�ѓ��e
�@�@�E�@���A�芼���̑��̊�{��
�@�@ �i�A�j�Љ���@�l�A���v�@�l��
�@�@�@�@�芼�A�s�ד��y�і@�l�̊T�v���Љ��Ă�����̂�Y�t���邱�ƁB
�@�@ �i�C�j��L�ȊO�̖@�l�A�C�Ӓc�̋y�ьl
�c�̂̊T�v���Љ��Ă�����̂�Y�t���邱�ƁB�l�ɂ��ẮA�ݗ��̎�|����������̂�Y�t���邱�ƁB
�i�Q�j�J�n�͂ɂ͎��̏��ނ�Y�t���邱�ƁB
�A�@�@�l�y�ю{�݂̑g�D�}
�C�@���ƌo�c�ҋy�ю{�ݒ��̗������y�ю{�݂ɏ]������E������
�E�@���ƌv��A�\�Z���y�щ�v���Y�ژ^
�G�@�����i�����A���p�j�K��
�I�@�����i�����A���p�j�_��
�J�@�{�ݒ��ݎ،_��
�L�@�{����}�i���ʐ}�j
�N�@�{�y�ѐݔ����̎ʐ^
�P�@�{�ݐݔ��ꗗ
�R�@�{�݈ē��}
�T�@�W����s���Y�̓o�L�듣�{
�V�@�n��Z�����ɑ��������̊J�ÂɊւ����
�X�@���̑��W�@�֓��ւ̓͏o���ނ̎ʂ�
�@�������A�C�̎��ƌo�c�҂̗������ɂ��ẮA���ɕʂ̎{�݂̓͏o�ɍۂ��Ē�o���A���̌�ύX�������ꍇ�A�ȗ����č����x���Ȃ����ƁB�Ȃ��A�{�ݒ��y�т��̑��̐E�����A�����̕ʂ̎{�݂���ٓ�����ꍇ�A���Y�������y�і���̑��ɁA��C�҂̗������y�і����Y�t���邱�ƁB
�U�@�ݒu�
�@�@�{�݂̐ݒu�ɂ��ẮA���̗v���������ƁB
�i�P�j�����͑ωΌ��z���͏��ωΌ��z�ł���Ȃnj��z��@�����炷�邱�ƁB
�i�Q�j�P�O�l�ȏ�̐l�������p�ł���K�͂Ƃ��邱�ƁB
�i�R�j��̋����́A�����Ƃ��ĂQ�ȏ�̐��тɗ��p�����Ȃ����ƁB
�i�S�j���Z�X�y�[�X�ɂ��ẮA�����҈�l�����苏���ʐςS�D�T�u�y�щ����ʐςV�u ���Œ��Ƃ��邱�ƁB
�i�T�j������n�K�ɐ݂��Ȃ����ƁB
�i�U�j�����̏o������͍d���Ȕ��Ƃ���ȂǁA�v���C�o�V�[�������悤�������ɔz�����邱�ƁB
�i�V�j�k�b���y�ё��k����ݒu���邱�ƁB���p�Ƃ���ꍇ�́A�v���C�o�V�[�������悤�z�����邱�ƁB
�i�W�j�H����ݒu���邱�ƁB
�i�X�j�����͒���Ɍ��������L���y�ѐݔ����m�ۂ��邱�ƁB
�@�@���ʏ��y�уg�C���������̂���K�ɒ���Ɍ�����������ݒu���邱�ƁB
�i10�j�U���W���A�����y�є��ʘH�����A���p�҂̈��S�m�ۂ�}�邱�ƁB
�@�@�܂��A���Ί�y�є�����ݒu����ȂǏ��h�@�����炷�邱�ƁB
�V�@�E�@��
�@�{�ݒ��y�ѕK�v�ɉ����Ă��̑��̐E����u�����ƁB
�@�E���́A�n��ɂ�����Љ���̑��i�ɔM�ӂ�L���A�Ɩ����s�ɕK�v�Ȕ\�͂�L����҂��[�Ă邱�ƁB
�i�P�j�{�ݒ��̗v��
�A�@�Љ���@��P�X���e���̂����ꂩ�ɊY������ҁB
�C�@�Љ�����ƂɂQ�N�ȏ�]�������ҁB
�E�@��L�A���̓C�Ɠ����ȏ�̔\�͂�L����ƔF�߂���ҁB
�i�Q�j���̑��̐E���̗v��
�@�@�\�Ȍ���Љ���厖�̎��i��L����҂ł��邱�ƁB
�W�@�E���̐E��
�@�@�E���͎{�݊Ǘ��ȊO�ɁA���p�ғ��ɑ����̋Ɩ����s�����ƁB���ƌo�c�҂͂��̎x�����s�����ƁB
�i�P�j���p�ҏ���
�@���p�҂̈��肵���������m�ۂ��邽�߁A�����S�ʂɂ킽�鑊�k�ɉ�������A���N�Ǘ��ɗ��ӂ��ʉ@���̉������s�����A���p�ҏ����̌���ɏ�ɓw�߂邱�ƁB
�i�Q�j�������i
�@���⑊�k�ɉ����铙�A�A�J�������s�����ƁB�A�J������Ȏғ��ɑ��Ă͐�����������u���邱�ƁB
�i�R�j�s�������Ƃ̘A�g���i
�@�{�݂̓K���ȉ^�c�̊m�ہA���p�҂̏����⎩�����i���̂��߁A�s�������Ə��������s���ȂǁA���݂̋��͑̐����\�z���邱�ƁB
�i�S�j�n��Z���Ƃ̊W�\�z
�@���p�҂�n��̕�������̂��߁A�Z���̈ӎv�d���āA��������n�抈�����s���A�ǍD�ȊW���\�z���邱�ƁB
�X�@������p��
�i�P�j�����g�p��
�@�@�A�@�����g�p���́A�������͒n��̎��ԓ������Ă�����z�Ȃ��̂Ƃ��邱�ƁB
�g�p��������ꍇ�ɂ́A���Y�g�p���Ɍ����������Z�����m�ۂ��邱�ƁB
�K���Ȏg�p������̂��߁A����y�ь������̕��@�ɂ��Ďs�������Ƌ��c������ȂǘA�g��}�邱�ƁB
�@�@�C�@�A�́u��z�v�Ƃ́A�ߗׂ̓���̏Z��ɔ�ׂĒ�z�ȋ��z�ł��邱�ƁB
�@�@�E�@�~���A����A�X�V�����ɂ�镉�S�͋��߂Ȃ����ƁB
�i�Q�j�H��A���p�i�
�A�@�H���A���p�i�������p������ꍇ�́A���p�҂̕��S�Ɍ����������e�̂��̂���邱�ƁB
�C�@���M���������ꍇ�́A������Ƃ��邱�ƁB
�i�R�j�i�P�j�y�сi�Q�j�̋��z�́A�����ŗ��p�҂ɖ������邱�ƁB�Ȃ��A�i�Q�j�ɂ��ẮA������������邱�ƁB
10�@�^�c�
�i�P�j�����ɓ������ẮA���p�҂ɑ��A�Љ���@��V�V���P���ɋK�肳��鏑�ʂ���t���邱�ƁB
�i�Q�j�����ɓ������ẮA�ۏؐl�����߂Ȃ����ƁB
�i�R�j�댯���̊Ǘ��͐ӔC�҂��ߓO�ꂷ�邱�ƁB
�i�S�j���p�҂̃v���C�o�V�[�d�����{�݉^�c�ɓw�߂邱�ƁB
�i�T�j�H�������ꍇ�́A�e��@�߂����炷��ƂƂ��ɁA�����]���ҁA�������A�H�i�A�H��A�H�����̉q���Ǘ��ɓw�߂邱�ƁB
�i�U�j�{�ݓ��̉q���Ǘ��ɓw�߂邱�ƁB
�i�V�j�{�ݓ��ɂ����銴���ǂ̔����y�т܂h�~�ɓw�߂邱�ƁB
�i�W�j�����͏T�R��ȏ�s�����ƁB
�i�X�j��ɒn��Z���Ƃ̑��ݗ����ɓw�߂邱�ƁB
�@�@�@�{�݊J������p�҂̏�{�݉^�c���̏����s���悤�w�߂邱�ƁB
�i10�j���p�ҁA�Z��������̋��ɑ��Ă͐ӔC�҂��ߓK�ȉ����ɓw�߂邱�ƁB
�i11�j���h�v����쐬���A���P�������{���邱�ƁB
�i12�j�E�������ɂ��ẮA�J����@�������炵�A���̌���ɓw�߂邱�ƁB
�i13�j���ƌo�c�҂́A���̎����ɂ�莖�ƌo�c�̓��������m�ۂ��邱�ƁB
�A�@�̎����A�_����ۊǂ���ƂƂ��ɁA�{�݂̎��x���Ɋւ��钠��ނ����邱�ƁB
�C�@�ݎؑΏƕ\�y�ё��v�v�Z���Ȃǎ��x�̏�v�N�x�I����R�����ȓ��Ɍ��y�ѐݒu�ꏊ�����ǂ���s�������ɕ��邱�ƁB
�E�@���p�҂ւ̏����J
�i14�j���p�Җ�������A�����I�ȏ������펞�̓K�ȑΉ��Ɏ����邱�ƁB
�i15�j���p�҂����炷�ׂ��K�����߁A���̏����O�ꂷ�邱�ƁB
11�@���̑�
�i�P�j���p�Ώێ҂́A��ʌ����ɐ����̖{���̂���҂Ƃ��邱�ƁB
�i�Q�j�J�ݒn�̎s�����ŗv�j�����߂Ă���ꍇ�́A�w�������炷��悤�w�߂邱�ƁB
�i�R�j�Љ���@��V�O���ɂ��A�K�v�ȗ��R�𖾂炩�ɂ��āA�W�s���@�ւ��玑���̒A�������茟���������߂�ꂽ�ꍇ�͋��͂����邱�ƁB
�i�S�j�Љ���@��V�Q���P���y�ё�Q���ɊY�������ꍇ�́A�{�݂̌o�c�̐������͒�~�𖽂����邱�Ƃ�����B
�@���̖��߂Ɉᔽ���Ď{�݂��o�c���������ꍇ�́A�Љ���@��P�R�P���̋K��ɂ��Y�����ɏ���������̂ł��邱�ƁB
�i�T�j���p�҂őg�D����鎩��������p�҂����p�����Ċ������s���ꍇ�́A���̎�����Ɋ������т���x�𗘗p�҂ɕ���悤�w���ɓw�߂邱�ƁB
�@�@���@��
�@�����P�S�N�U���Q�P������{�s����B
�@�@���@��
�@�����P�V�N�R���P������{�s����B
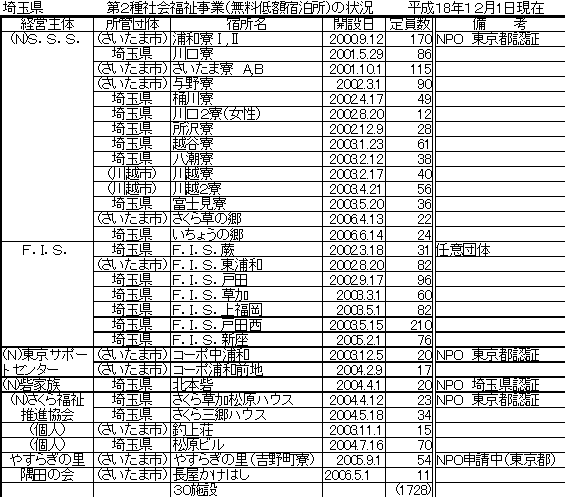 �@
�@
��ʌ��̃z�[�����X�x���{��̊T�v ��ʌ��������Љ����
�P�@���k���ɂ�鑍�����k
�͐�~���Ő�������z�[�����X�ɐ��������A�������k���s���B���k�̌��ʂɂ��A�h�����̗��p�ē��A�����ی쓙�̊e��{��̊��p�ɑ��鏕�����s���ƂƂ��ɁA�ց@�@�W�@�ւƂ̘A�g��}��B
�k�����P�V�N�x�l����s�A�˓c�s�Ɋe�Q���z�u
�@�@�@�@�@�@�@�@���ׂP�C�O�O�V�l�ɖʐڂ��A�{�ݓ����P�T�l�A���@�P�P�l
�Q�@�����c�������@�l�i�m�o�n�j�����������
�@�z�[�����X��ΏۂƂ����x���������s���m�o�n���A���k���ƁA�����z�t�A���C���Ɠ������{�����ꍇ�ɁA���Ƃɗv�����o�����������B
�⏕���Q�^�R�A�P�c�̓�����⏕�z����Q�O�O��~
�R�@�ٌ�m�ɂ��@�����k
�@�z�[�����X�̎�����W����v���ƂȂ�؋���蓙���������邽�߁A�����ی���A�h�������ɓ������Ă��錳�z�[�����X�ɑ��A�ٌ�m�ɂ��@�����k�����{����B �@�@�@��ʕٌ�m��ɕٌ�m��h���˗��@�������{�B
�k�����P�V�N�x�l�Ώێ҂R�V�l�B���k��A���Ȕj�Y�̎葱�������s�����B
�S�@�E�Ƒ��k������
�@�n���[���[�N�ƘA�g���āA��C�̐E�Ƒ��k���ɂ�鑊�k�A���l���̒A�E�ƌP�@�������{���A�z�[�����X�̏A�J�������x������B �@
��ʌ��ٗp�c��Ɉϑ��@���k���Q��
�k�����P�V�N�x�l�Ώێ҂X�P�l�B���A�S�U�l���A�J���J�n�����B
�T�@�z�[�����X�����x�����i����
�@���z�[�����X�x���v��̐��i��}��ƂƂ��ɁA�Z�~�i�[�����J�Â��ăz�[�����X���Ɋւ���[�����s���A�s���A���Ԏx���c�́A�n��ɂ��z�[�����X���x������̐��̍\�z��}��B
�z�[�����X�ɑ����Ζ���ď���̎��{�ɂ���
�P �ړI
�z�[�����X�Ɋւ�鎖�̂⎖���̔����\�h�̂��߁A�܂��A��i�Ɗ���������
���Ȃ�Ζ����}���邱�Ƃ���A�����e�s�ŏ�������{���A�z�[�����X�̏c
���⑊�k�A�ی쓙���s���B
�Q ���{��̍�ʌ��A�����e�s�i�R�R�s�j
�������s�A��z�s�A�F�J�s�A�s�c�s�A�����s�A����s�A�є\�s�A���{�s�A�{���s�A�����R�s�A�t�����s�A���R�s�A�H���s�A�����s�A�[�J�s�A�z�J�s�A�n�s�A�˓c�s�A���Ԏs�A�����s�A�u�؎s�A�a���s�A�V���s�A����s�A�v��s�A�k�{�s�A�����s�A�ӂ��݂̎s�A�@�c�s�A��ˎs�A�K��s�A�߃����s�A�g��s
�R ���{���������P�V�N�P�Q���Q�O���`�P�Q���Q�V��
�i�ꕔ�A���̊��Ԃ̑O��ł̎��{����j
�S ���{���@�s�E���Q�����x�̑̐��Ŏs�������A�{�l�ɒ��ږʐڂ���B
���̏��]�ɂ��A�h�����ւ̓������Ë@�ււ̎�f�������߁A�K�v�ȕی���s���B
�T ���̑��˓c�s�ɂ��ẮA���s�����Ŏ��{����B
�k���{�����l�����P�V�N�P�Q���Q�Q���i�j�ߑO�X���`�ߌ�S��
�k���{�̐��l�s�E���R���y�ь��E���P��
�y�z�[�����X�x���c�̊�����⏕���ƊT�v�z
�P�@�⏕�Ώےc��
�@�@�����ɁA�芼�ɋL�ڂ��ꂽ��������L���A�����Ŋ������Ă�������c�������@�l
�Q�@�⏕�Ώێ���
(1) �z�[�����X�̎����ɗL���ƔF�߂��鎖��
(2) �����̃z�[�����X�Ɋւ��闝���𑣐i���鎖��
(3) �z�[�����X���x�����銈�����������鎖��
(4) ��L�ȊO�ɁA���ɒm�����K�v�ƔF�߂鎖�Ɓi��������ړI�Ƃ��鎖�ƁA������z�h�����Ƃ̉^�c�y�т���ɕt�����鎖�Ƃ͑ΏۊO�j
�R�@�⏕���@�Ώیo��̂Q�^�R�@�i��c�̂Q�O�O��~������j
�S�@�\������t����
�@�@�����P�W�N�V���R���i���j�`�V���R�P���i���j
�T�@�\������o��
�@�@��ʌ��������Љ���ۃz�[�����X���S��
�@
�����P�V�N�x����
�m�o�n�@�l�����������A�J�x���Z���^�[�@
�@�@�n��Z����ΏۂƂ������y�[�����Ɓi�f���u����j
�m�o�n�@�l��ʃ`�[���P�A���ہ`��
�@�@�z�[�����X��ΏۂƂ����x�����Ɓi�������k��j
�i�P�j�����z�[�����X��
���������P�R�N�W���@�P�S�N�W���@�P�T�N�P���@�P�T�N�W���@�P�U�N�W���@�P�V�N�W��
�l���@�@�@�U�Q�V �@�@�@�V�S�V�@�@ �W�Q�X �@�@�@�V�P�P �@�@�@�V�T�R �@�@�@�W�O�W
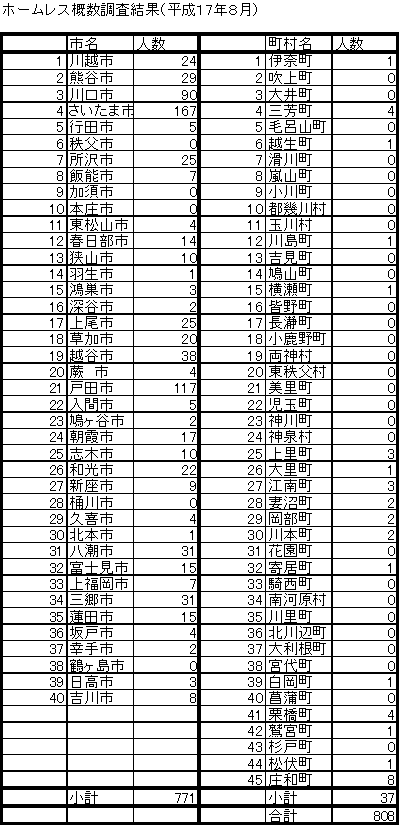
��ʌ��Љ���R�c��c���^
�@
�����@���@�����P�T�N�P�P���P�W���i�j�ߌ�Q���`�S��
(3)�@��ʌ��z�[�����X�x���v��̍���ɂ���
�y�����ǁz
�@�Љ���ے����玑��3-1�y��3-2�ɂ�����
�@
�y���^�����z
�i���}���ψ����j
�@�z�[�����X�̕��X�ɑ���l�X�Ȏ����A���̂ȂǁA�l�����ǂ����̂��Ƃ������Ƃ��܂߂āA�[���ȏ��L�����Ă���B�����ł�800�����̕���������B���̕��X�ɑ���x���̌v������ꂩ������Ă����Ƃ������ƂŁA����ɂ��Č�ӌ����������������B
�@
�i��؈ψ��j
�@�z�[�����X��829������Ƃ������A�ǂ��ɂ���̂��B
�@
�i�Љ���ے��j
�@���N�̂P���Ɏs�����̐E�����ڎ��Œ������Ă���B�w�⋴�̉��A�����ȂǗl�X�ȂƂ���ɂ���B�s�����ʂł́A�������s��211���A�˓c�s��97���A����s��71���A�����s��30���A��z�s��29���A�n�s��29���A�@�c�s��25���A�z�J�s��23���Ȃnj���ɑ����B
�@
�i��؈ψ��j
�@���̒��ŁA�����ɂł��a�@�ɓ���Ȃ��Ƃ����Ȃ��A��ÓI�ȑΉ����K�v�Ƃ������͂���̂��B
�@
�i�Љ���ے��j
�@�ڎ����������ŁA829�l�ɑ��Ă͒��ڐ��|�������ď��m�F�����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�m�F���Ă��Ȃ��B
�@
�i��؈ψ��j
�@�����_�ł́A�����o���Ȃǂ͂Ȃ��̂��B
�@
�i�Љ���ے��j
�@�s���ł�NPO�Ȃǂ������o�������Ă��邪�A��ʌ��ł͌��݂Ȃ��B
�@
�i��؈ψ��j
�@�a�C�̕������e����v����Ȃ����B�Ⴆ�ΐ����|��Ă���l�ȂǁB���ꂩ��~�Ɍ������Ă������E�E�E�B
�@
�i�Љ���ے��j
�@�ی����Ȃǂŏ��k�A���N�f�f�Ȃǂ��s�����Ƃ����������Ă���B�e�����������ł́A�����ی��K�p����Ƃ����`�őΉ����Ă���B����͖{�l���\��������̂����B
�@
�i�H�R�ψ��j
�@�z�[�����X��ɂ��ẮA���y�э��̂悤�Ȋ���������B�A�J����ӗ~�����邩�Ȃ����Ƃ������Ƃ�O��ŕ����l���Ă���悤�Ɏv���B�z�[�����X���H�㐶�������Ă���킯�ŁA�܂������������X����|���邱�ƁA���ꂪ�s���Ƃ��Ă̎d�����Ǝv���B��������ӗ~�̂Ȃ��l�͕����Ă����Ƃ������������ĂȂ�Ȃ��B���e�{�݂������āA�����I�Ɏ��e����Ƃ������Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����B
�@
�i�Љ���ے��j
�@�������ۂɃz�[�����X���������Ă���r��ɂ��s�����B�܂��A�����ɂ��s�������A�ŏ������������Ȃ��B����������Ɓu�����ɂ����v�ƕs�M�̖ڂŌ����A�b�������Ă��炦�Ȃ��B���݁A���k�������ƌ˓c�ɂQ���Âz�u���āA�����A�����S�苭�����|�������Ă���B�H�㐶�����D���ł���Ă���̂ŁA���܂��Ă����ȂƂ����l�����ɑ����B�����������X�������I�ɖ��Ԃ̏h�����Ɏ��e����Ƃ������Ƃ͓���A�{�l�̈ӎv���m�F���Ă���łȂ��Ƃł��Ȃ��ł���B�z�[�����X�̎����𑣂��Ƃ������Ƃ��珉�߂āA�����ی�őΉ�����Ƃ������Ƃ��s������e�����������Ő^���ɑΉ����Ă��āA�{�݂Ɏ��e���邱�Ƃ܂ł͍s���Ă��Ȃ��̂�����ł���B
�@
�i�H�R�ψ��j
�@�͐�~�̋��̉��Ȃǂ͌��I�ȏꏊ�ł���A�������L���Ă���B�����������Ƃɑ��ẮA�L���Ȏ�i���Ƃ��̂ł͂Ȃ����B
�@
�i�Љ���ے��j
�@�s�����ł����낢��ȕ���ƘA�g���Ă��āA�͐�~�Ȃǂł͑䕗���J�Ő����o��Ɗ댯�Ȃ̂őҔ����w�����Ă��邪�A���Ȃ��Ȃ��Ă͂܂������Ƃ������ƂŁA�Ȃ��Ȃ��v���ɂ܂����Ȃ��ł���B
�@
�i���c�ψ��j
�@�����Z��ł���߂��̌����ɂ��z�[�����X�̕�������B������Ȃǂ����Ƃ����Ȃ���Ƃ������ƂŁA�s���ɂ��肢���Ă��Ή����d��Ă��Ȃ��B�܂����̌����Ȃ̂ł��ꂳ�q�ǂ���A��Ă�����A�����Ȏq�ǂ����݂�ȂŗV��ł���Ƃ���ł���B���ꉽ��������Δ��ɖ��ƂȂ�B�����I�ɂ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�������Ȃ���d���ɂ�����Ƃ��A���e����Ƃ��A�������Ȃ��Ǝ����Ɍq����̂ł͂Ȃ����B���������Ă���B
�@
�i�Љ���ے��j
�@�������s�ɂ��ẮA���A�Ċm�F�������A10�N�̎������@�ł���z�[�����X�̓��ʑ[�u�@�̍Ō��11���ɁA�u�����̗p�ɋ�����{�݂̓K���ȗ��p�̊m�ہv�Ƃ����Ƃ���ŁA�s�s�����Ȃnj����̗p�ɋ�����{�݂��Ǘ�����҂́A�K���ȗ��p���W������Ă���Ƃ��͕K�v�ȑ[�u���Ƃ��̂ŁA���̕ӂ�����O�ꂵ�Ă��������B
�@
�i�H�R�ψ��j
�@���������_���m�����Ȃ��ƁA��{�I�Ȗ��̉����ɂȂ�Ȃ��B�������e�{�݂�p�ӂ��Ȃ��ƒǂ��o�������ƂɂȂ�B�{�݂�p�ӂ���A�Z�ނƂ��낪����̂ɂȂ����Ȃ��̂��A�Ƃ������������藧�̂Ŏ{�݂͕K�v�ł���B
�@
�i���}���ψ����j
�@��̓z�[�����X�̕��X�̈��S�̖��A��͒n��Z���̈��S�̖��Ƃ������ƂŁA���ɓ���_������B�����I�ȑΉ������蓾��̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂƓ����ɁA�{�l�̈ӎv���ǂ����d����̂��Ƃ������Ƃ͎Љ���@�̊�{�I�ȗ��O�Ȃ̂ŁA�����ɒ�G����킯�ɂ��������A�ɂ����䂵�ł���B
�@�Ȃ��A�{�݂ւ̏h���҂�����Ƃ̐��������������A�{�݂͊��ɏ������Ă���Ƃ������Ƃ��B�܂��A�������邱�Ƃ��l���Ă����Ƃ������Ƃ��B
�@
�i�Љ���ے��j
�@���Ԃ̏h����������18��������A��1,300���������Ă���B�܂��A��ʌ��Ƃ��ẮA�z�[�����X�̐�����s���ł͂���قǑ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�V���ɐ�������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���Ԃ̏h�����̗͂���Ȃ���ƍl���Ă���B
�@
�i���}���ψ����j
�@�x�@�Ƃ̘A�g���K�v�ɂȂ��Ă���Ǝv���̂ł�낵�����肢�������B
��ʌ��c��
�y�@�����P�U�N�@�P�Q���@����-12��09���|05���@�z
P.370�@�� ��\��ԁi�Γc���c���j
���ɁA�z�[�����X���ɂ��Ăł������܂��B
�@�����̌������o�ς�ٗp���w�i�ɁA���炩�̗��R�ɂ��A�z�[�����X�ƌĂ���ԂƂȂ邱�Ƃ�]�V�Ȃ�����Ă���l�X���������Ă���܂��B���Ƃ��傫�Ȍ����Ƃ��ċ������܂����A�؋�������A���̋������\�����Љ���𑗂邱�Ƃ�����ɂȂ�ȂǁA�l�X�Ȏ���y�ь����ɂ��z�[�����X������]�V�Ȃ������l���������݂��Ă���̂ł��B
�@�����J���Ȃ������\�ܔN�Ɏ��{�����z�[�����X�̎��ԂɊւ���S�������ɂ��ƁA�S���̃z�[�����X�̐l���͓ܐ��S��\�Z�l�ŁA�s���{���ʂł͑��{�����玵�S�\���l�A�����s���Z��O�S�Z�\��l�A���m�������S��\��l�ƁA��ɑ�s�s�ɏW�����Ă��܂����A���@�ň��m���̖��É��s�ɍs�����Ƃ��A���H�̒��������тɃu���[�V�[�g�̌Q�ꂪ�A�����Ă������܂����B�ʍs�����Ƃ����Ă̏��������ł��������߁A���ʂ����悭���邽�߂ɓ�����̃V�[�g���J���Ă����̂��قƂ�ǂł������܂����̂ŁA�����̃z�[�����X���Z��ł���̂������܂����B������グ�܂��ƍ������H�ł��邽�߂ɉ����Ƃ��ė��p����A�������������A�܂��J����������ꏊ�Ƃ��ďZ���������Ă���܂����B���ɂ́A�Ƃ̌`�Ƀu���[�V�[�g���A���Ƀe���r����������ł������ƒ�Z�����Ă��邩�̂悤�Ɏv�����̂�����܂����B�܂��A�����イ�̌������ɂ��Ƃ���ǂ���Ƀu���[�V�[�g������A�����Ƃ���A�r���X�̒��S���ɋ߂����Ƃ�����A�ڂɂ���ɂ͖��f�ȂƂ���Ƃ������Ƃŋ��k���Ă���܂����B
�@�ȏ�̂悤�Ɉ��������ďq�ׂ����Ă��������܂������A�z�[�����X�̖��͎��ӓs�s�ɍL����������Ă���A����ł́A�z�[�����X�ւ̎E�������ɏے������悤�ȎЉ�I�ȕΌ����L����ȂǁA�S���I�ɐ[���ȎЉ���ł���ƌ����܂��B
�@��ʌ��ł��A�����\�ܔN�Ɍ����J���Ȓ����̈�Ƃ��Ē������s�����Ƃ���A�����ł͔��S��\��l�̃z�[�����X���m�F����܂����B�����̃z�[�����X����������n��́A�������s��S�\��l�A�˓c�s��\���l�A����s���\��l�ƂȂ��Ă���A�܂��N��z�͌\����\����S�̂̌܁Z�p�[�Z���g�A�Z�\����Z�\����E�܃p�[�Z���g���߁A������͐�~�ɂ����đ����̃z�[�����X�̊m�F�������ȂǁA�S�������Ɠ��l�̌X���������܂��B
�@�����J�s���ł����N�O�ɁA�����̌��O�g�C���̒����A���̌��O�g�C���͎Ԉ֎q�ɏ��������҂�g��҂̕��X�ɂ����p�ł���悤�ɐv����Ă������߁A�g�C���̃X�y�[�X���L���̂ŁA�z�[�����X���i�{�[����z�c�Ȃǂ��������݁A�������炩�����������荞���Ƃ�����܂����B�g�C���ɓ���Ȃ��ƒʕ���A�삯�����Ƃ���A�z�[�����X�����ɂ����Ƃ̂��Ƃł���܂����B�ق��ł����̂悤�ȏo�������N�������Ƃ�����ƕ����y��ł���܂��B
�@�z�[�����X�Ɏ������v���Ƃ������܂��ẮA�|�Y��a�C�A�����A����ȂǂŎd�����ł��Ȃ��Ȃ�ȂǁA�A�J�ӗ~�͂�����̂̎��Ə�Ԃɂ��邱�ƁA��Â╟���Ȃǂ̉��삪�K�v�ł���Ȃ���Љ�I�ȑ����������A���邢�͏��ʂ̎����g���𖾂炩�ɂ��Ȃ��ȂǁA�Љ�������ۂ��邱�ƂȂǂ��������܂��B�����������ŁA�������ɂ��z�[�����X�ɑ���W�c�\�s�����ɏے������悤�ȎЉ�I�r�����w�i�Ƃ��ċ������邱�Ƃ���A�z�[�����X�x���Ɍ����đ���u����K�v������Ǝv���܂��B
�@��ʌ��ł́A���̃z�[�����X�����̎x�����Ɋւ�����ʑ[�u�@�����ꍀ�Ɋ�Â��A�����\�Z�N�O���ɍ�ʌ��z�[�����X�x���v������肵�A���ۑ�̉����Ɍ�������g���n�܂��Ă���܂��B�������A�Љ�������ۂ��Ă���z�[�����X���d���⎩���������������߂��Ă������Ƃ͗e�Ղł͂���܂���B�������悤�Ƃ��Ă��A�ӗ~���������Ȃ���Ȃ炸�A�g���𖾂����Ȃ��Ȃǂł́A�N���g���̕ۏ����ďA�J�����Ă����̂��A�ۑ�͂�������Ǝv���܂��B
�@�����ŁA���N���������ɂ��q�˂��������܂��B
�@�z�[�����X�ɐH���A�Z���A�����Ĉ�ÂȂǂ̌��N�ɂ��Ăǂ̂悤�Ɏx������Ă����̂��B�����āA�Љ�A�̎x����Ȃǎ����Ɍ������{���[�����������f���������܂��B�����āA���|���Ȃǂ̓{�����e�B�A��m�o�n�̋��͂��K�v�Ǝv���܂����A���Ƃ̋��͑̐��ɂ��Ă����f�����������܂��̂ŁA���N���������̌䏊�������肽���Ǝv���܂��B
���ɔ\�͌��N���������@�䎿��܁A�z�[�����X���ɂ��Ă�������\���グ�܂��B
�@�z�[�����X�̎����x���ɂ��܂��ẮA�c����w�E�̂Ƃ���A�Z���A���N�A�A�J�Ȃǐ������̖�������Ă���܂��B���̒��ł��A�܂����肵���Z���̊m�ۂ��������ŗD��ɉ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƍl���Ă���܂��B���̂��ߌ��ł́A�͐�~������Ȃǂɋ��Z����z�[�����X�ɑ��A���k���╟���������Ȃǂ̊W�E�������Ȃ��琶�����k���s���A�����ی쐧�x�Ȃǂ����p���������E��z�h�����ւ̓����ȂǁA�Z���̊m�ۂɂ��Ďx�����Ă���Ƃ���ł��B���̂悤�ɐ����ی���ďZ�����m�ۂ��Ă����������Ƃɂ��A�H���A�ߕ��A��ÂȂǁA�������Ă�����ŕK�v�ȉۑ�����������ł�����̂ƍl���܂��B
�@���ɁA�Љ�A�̎x����ɂ��Ăł������܂����A�����\�ܔN�̑S�������ɂ��܂��ƁA�z�[�����X�̘Z���ȏ�̕����A�J�̊�]�������Ă���Ƃ������ʂ��o�Ă���܂��B�����ŁA�����\�ܔN�x�Ɍ��ٗp�c��̌䋦�͂����������A�E�Ƒ��k���ꖼ�ɂ��A�J�x�����n�߂܂����Ƃ���A�l�\���l���A�E�Ɍ��ѕt�����ʂ��������܂����B�\�Z�N�x�ɂ́A�X�ɐE�Ƒ��k�����ꖼ�������ď[����}��܂����B�܂��A�z�[�����X�ɂȂ��������Ƃ��āA���d���Ɋׂ������Ƃ������F�߂��܂����Ƃ���A�ٌ�m�ɂ��@�����k�Ȃǂ������Ď��{�������܂��āA�����𑣐i���Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@���ɁA�[�������ɂ��Ăł������܂����A�z�[�����X�ɑ���Љ�I�Ό��́A�l���ɂ������傫�Ȗ��ł������܂��̂ŁA�W���ǂƘA�g��}��Ȃ���A�Ό��̉����Ɍ������[�������Ɏ��g��ł܂���܂��B
�@���ɁA�Z���Ƃ̋��͑̐��ɂ��Ăł������܂��B�z�[�����X�̎����x���𐄐i���邽�߂ɂ́A�c����̂Ƃ���A���|���Ȃǂ�ʂ����X�����k���ԃp�g���[���Ȃǂ��s���{�����e�B�A�A�m�o�n�ȂǂƘA�g���邱�Ƃ��K�v�ł���ƔF�����Ă���܂��B���̂��߁A�����\�Z�N�x�\�Z�ł��F�߂��������܂��������c�������@�l����������Ƃɂ��܂��āA�z�[�����X�̎����x�����s���{�����e�B�A��m�o�n�Ȃǂ̈琬�ɓw�߂Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@���Ƃ������܂��ẮA�s�����A�x�@���͂��߂Ƃ���W�@�ցA�m�o�n�ȂǑ����̕��X�̌䋦�͂����������Ȃ���A�z�[�����X���̉����Ɏ��g��ł܂��肽���Ǝv���Ă���܂��B
�y�@�����P�T�N�@�@�Q���@����-02��25���|03���@�z
P.239�@�� ��\��ԁi�`�N���c���j
���ɁA�z�[�����X��ɂ��Ď��₵�܂��B
�@���́A�����\��N����̈�ʎ���Ńz�[�����X���ɂ��Ď��₵�܂������A�����̘J�����H�����A���N���������́u���̓����܂��đΉ�����v�Ɠ��ق��Ă��܂��B�����\�ܔN�x�\�Z�Ƀz�[�����X��̐��i���v�コ��Ă������Ƃ́A�u���̊�������܂��B�����\�l�N���������Ƀz�[�����X�̎����̎x���Ɋւ�����ʑ[�u�@���{�s����Ă��܂��B�����̐܂ɂ�������炸�A�w�ɁA�����A�H��ȂǂŒi�{�[���ɂ���܂��Đ������Ă���z�[�����X���l����ƁA�܂��ɐl�����ł���A�����ی�̓K�p��{�ݓ����Ȃǂ̑[�u�A��Â�����k�����̐ݒu�ȂǁA�s�����ƒ�g���ĐϋɓI�Ɏx�����Ă������Ƃ̕K�v����Ɋ����Ă��܂��B�z�[�����X�̒��ɂ́A�����s���Ŋ�Ƃ̓|�Y�A���X�g���Ŏ��Ƃ����l����ނȂ��H�㐶���҂ɂȂ��Ă���P�[�X������܂��B�������̂���x������u����i�K�ɂ���Ǝv���܂����A�m���ɂ��l�������f�����܂�
P.259�@�� �y���`�F�m��
���ɁA�䎿��攪�̃z�[�����X��ɂ��Ă̂��q�˂ł������܂����A�����A�s���Ƃ����Љ�I�v��������A�{���ɂ����Ă��z�[�����X���}�����Ă���܂��B�܂��A�����Ɋ������܂�鎖�Ԃ���������ȂǁA�H�㐶����]�V�Ȃ�����Ă�����ɑ���x���́A�ꍏ���P�\�Ȃ�Ȃ��ۑ�ƔF�����������Ă���܂��B����܂Ő����ی�𒆐S�Ƃ��ĐϋɓI�ȕی�A�~�ςɓw�߂Ă܂������Ƃ���ł���܂��B�܂��A��N���ɂ́A�E���Ɏw�����A�����������̉��ɂ���z�[�����X�̕�����l�ł������~�ς��邽�߁A�s�ƈ�̂ƂȂ��ď������Ƃ�����������܂��B
�@���݁A�����̖��ԏh�����ȂǂŖ���S�l�̕������ɕی����Ă���A���̌����c�����A����̑�ɐ��������߂ɁA�h�����𗘗p����z�[�����X�ł��������ɑ��A������蒲�������{�������܂����B���̌��ʁA�d���̌�����X�g���Ȃǂ������Ƃ�����������A�܂��A�A�Ƃւ̈ӗ~��������������l�����߂Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B
�@�z�[�����X���̉����ɂ́A�ی��E��ÁE�������͂��߁A�ٗp�A�Z��ȂǕ��̍L���Ή����K�v�Ȃ��Ƃ���A�����\�ܔN�x�ɂ����܂��Ă̓z�[�����X�S���g�D��V���ɐݒu���A�S���������Ď��g��ł܂���܂��B�����āA���k�ƕی��S�������告�k����A�J���k�A���l���̒Ȃǂ��s���E�Ƒ��k�����z�[�����X�̑�������̎s�Ȃǂɔz�u���A�������̂��鎖�Ƃ�i�߂邱�ƂƂ������܂����B�z�[�����X���́A�l���ɑ傫���������Љ�S�̂̉ۑ�ł������܂��̂ŁA�����͂��Ƃ��A�s�����A�x�@���܂ފW�@�ցA�m�o�n�ȂǑ����̕��X�̋��͂����������Ȃ���A���̉����ɑS�͂Ŏ��g��ł܂��肽���Ƒ����܂��B
�y�@�����P�S�N�@�P�Q���@����-12��12���|05���@�z
P.357�@�� �l�\�ԁi���F��c���j
���ɁA�z�[�����X��ɂ��Ă��q�˂������܂��B
�@����A�F�J�s�Ŕ��������z�[�����X��Ԃɂ������l�ɑ��鏝�Q�v�������͑�ϒɂ܂��������ł���܂����B�ɂ��܂��ƁA�S���Ȃ�����Q�҂̕��͈�N�ȏ�O���玖���̂������ꏊ�Ő������Ă����悤�ł���܂��B�����������̐E�������x���ڐG�Ɏ��݂āA����Ƒ��k�ɉ����钛���������Ă������̂��ƂŁA���������ꍇ�̑Ή��̓�����F�������Ƃ���ł���܂��B
�@�{�������N�㌎�Ɏ��{�����z�[�����X���ɂ��Ă̒����ł́A�S���ŖS�l�\���l�ƁA�O�N�̒����Ɣ�r���ĕS��\�l���������Ă���ƕ����Ă���܂��B���̏Z��ł��鉱��s�ɂ����Ă��A�z�[�����X�̐l��ΏۂƂ������Ԃ̏h���{�݂��{�N�J�݂���܂������A�����҂́A����s���͂��ߎ��ӎs��������������Ă��Ă���܂��āA���ɋ��Ȃ���Ԃɂ���܂��B��������z�[�����X�ւ̑�́A��s�����ʼn����ł�����ł͂Ȃ����Ƃ���A���Ǝs�������A�g�����Ή����K�v�ł���Ƌ����Ɋ����Ă���܂��B�����̌o�Ϗɂ����āA������z�[�����X�ɂȂ�l�������X�ɑ����邱�Ƃ��\�z����钆�ŁA�{���Ƃ��Ă��ϋɓI�Ȏ�g�����߂��Ă��Ă���܂��B�����ŁA��ʌ��ɂ�����z�[�����X��ɂ��Č��݂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��s���Ă���A�܂��A����ǂ̂悤�ȑ���l���Ă���̂��A���N���������ɂ��f�������������Ǝv���܂��B
P.376�@�� ��㏻�q���N��������
���ɁA�䎿��\�A�z�[�����X��ɂ��Ă�������\���グ�܂��B
�@�܂��A�z�[�����X�ɑ��錻�݂̑Ή��Ƃ������܂��ẮA��ʂ̐����ی�҂Ɠ��l�ɓK�ȕی���s���悤�e�������������w�����Ă���܂��āA�㌎������݁A���S��\��l�̕������Ԃ̏h�����Ȃǂŕی���Ă���܂��B�܂��A�����������Q�v�������ɍۂ��܂��ẮA�S���E���̌��C����J�Â��A�z�[�����X�̏c���Ƒ��k��ی��K�ɍs���悤�A���߂Ď��m�O���}��܂����B
�@���ɁA����̑�ł������܂����A�����������ɐ�C�E����u���A����ɂ�鑊�k��ی���s�����Ƃ��������Ă���܂��B�܂��A�A�ƂɌ��т��e��̎��i�擾�Ȃǎ����Ɍ������ϋɓI�Ȏx�����s�����߁A���݁A���ăz�[�����X�ł������l�����ɑ��A����܂ł̏⍡��̐����ɂ����ĉ������҂��Ă��邩�Ȃǂɂ��Čʂ̖ʐڒ��������{���Ă���܂��B
�@�����z�[�����X�ւ̋�̓I�Ȏx���ɓ�����܂��ẮA�s�����ƈ�̂ƂȂ����ٗp�A�Z��A�����A�ی��ȂǕ��L������ł̎�g���K�v�ƂȂ�܂��̂ŁA�s�����ɑ��A�S�������̐ݒu�⋭�����|���܂��ƂƂ��ɁA�x�@�A�a�@�A�n���[���[�N�A���H������Ȃǂ̊W�@�ւɂ��A��������c�ɂ����āA���ꂼ��̖����𖾂炩�ɂ��Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B�z�[�����X�ƂȂ邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ���X�ւ̎x���͎Љ�S�̂̉ۑ�ł������܂��̂ŁA�����͂��Ƃ��W�@�ւƂ̘A�g�𖧂ɂ��āA���̉����Ɏ��g��ł܂���܂��B
�y�@�����P�S�N�@�@�X���@����-10��03���|05���@�z
���ɁA�z�[�����X���ɂ��Ă��f�����������܂��B
�@���Ă̓��{�o�ϐ����́A�Y�Ƃ̔��W�ƂƂ��ɍ��������̌��㓙�ɑ傫���v�����A��X���l�X�Ȑ����̖ʂł�������Ă��܂����B�������A�o�u���o�ς̕����̍����A���݂̌o�ϕs���A�ٗp���̈����E��́A�������̐����ɕs���������炵�A�܂��l�X�Ȑ[���Ȗ���ł���܂��B
�@�����������A������z�[�����X�ƌ�����l����������A�o�ϕs���̂�������ăz�[�����X��]�V�Ȃ�����Ă���l�X�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��������Ƒ����܂��B�z�[�����X�́A�����J���Ȃ̒����ɂ��ƁA��N�㌎�����݂ł��S���ɓl��l�Ƃ���Ă���܂��B����̌i�C�̓����ɂ���ẮA���̍X�Ȃ鑝�������J�������Ƃ���ł��B
�@�܂��A�z�[�����X�͎�s�������łȂ��n���s�s�ł��������Ă���Ǝf���Ă���܂��B���̏Z�ތ˓c�s�ɂ����Ă��A������͐�~���ɂ��������̃z�[�����X������A�s���Ƃ��ĕ����I�ɉ��炩�̎肾�Ă�A�v���[�`���ł��Ȃ����̂��A�����g�A���X�v�����߂��炵�Ă���܂��B�܂��A�s���̕��X��������l�̑��k�₨�b�������������Ƃ�����܂��B�z�[�����X��Ԃł���A��s���A�ʍs�l�Ƃ̃g���u���ȂǁA���X�̌������������z�������Ƃ���ł���A�܂��H����Z�܂��̊m�ۂƂ�������{�I�Ȑ�����]��ł���͂��ł��B�܂��A�z�[�����X�̐l�����͌��݂̏�Ԃ����Ƃ��E�������A�����Ɍ����Ă�����x�撣���Ă݂����Ǝv���Ă���l�����Ȃ��Ȃ��͂��ł��B���ɂ����Ă��z�[�����X�@�Ă��������A�悤�₭����n�������̂̐ӔC�ɂ����Ă��̑i�߂��悤�Ƃ��Ă���܂��B
�@�����ł��q�˂��܂��B�����Ƀz�[�����X�͂ǂ̂��炢����̂��B�܂��A����ł͂ǂ�ȑs���A�܂�����ǂ̂悤�ȑ��}���Ă����̂��B
P.408�@�� ��㏻�q���N��������
���ɁA�䎿�⎵�A�z�[�����X���ɂ��Ă�������\���グ�܂��B
�@�܂��A�����̃z�[�����X���ɂ��Ăł������܂����A�����\�l�N�㌎�Ɏ��{�������܂������̒����ł́A�l�\�܂̎s�����Ŏ��S�l�\���l���m�F����Ă���܂��B
�@�܂��A����ł̑�ɂ��Ăł������܂����A�s�����ƘA�g���A����ɂ�鑊�k�E�w�����邢�͏h�����̏��Ȃǂ��s���Ȃ���A��Ƃ��Đ����ی쐧�x�őΉ����Ă���A���ݔ��S��\��l�����@�▯�Ԃ̏h�����Ȃǂŕی���Ă���܂��B
�@���ɁA����̑Ή��ɂ��Ăł������܂����A��ʐ��������z�[�����X�����x���@�ɂ����܂��ẮA�ٗp�A�Z��A�����A�ی��ȂNJe��̎{��𑍍��I�ɐ��i���邱�Ƃ����߂��Ă���܂����Ƃ���A�S���I�ɑΉ����Ă������߂̒����A����c�ƕ����āA�s�����y�ьx�@���A�a�@�A�n���[���[�N���̊W�@�ւƘA�g���A��̓I�ȑ��i�߂邽�߂̘A��������c��������ȂǁA�z�[�����X��̐��i�̐��𐮂����Ƃ���ł������܂��B
�@�܂��A�ߋ��Ƀz�[�����X�ł������l�����ɑ��A��������]�݁A���㉽�����҂��Ă��邩�Ȃǂ̒����̏��������i�߂Ă���܂��āA���̒������ʂ܂��A�W�@�ւƂ̘A�g��}��Ȃ���A�z�[�����X�̎����x���ɐϋɓI�Ɏ��g��ł܂��肽���ƍl���Ă���܂��B
�y�@�����P�Q�N�@�P�Q���@����-12��12���|03���@�z
P.214�@�� ��\��ԁi���ؐm�c���j
���ɁA�z�[�����X��Ɛ����ی�s���̏[���ɂ��Ďf���܂��B
�@�����Ȃ����N�\�ɂ܂Ƃ߂��������ʂł́A�S���̃z�[�����X�̐��͓l���A�������O�̒������ʂ���l��l�������܂����B����̒��������{�s�Ɛ���s�͒����Ώۂɉ������܂����B�z�[�����X�̋}���̗v�������X�g����|�Y�ŐE�������A�Z����ǂ�ꂽ���ʂł��邱�Ƃ́A���Ɠ����s�Ȃǂł���z�[�����X���A����c���u�o�ρE�ٗp��̈��������z�[�����X�������Ă���v�ƕ��͂��Ă��邱�Ƃł����炩�ł��B��N�܌��A�����z�[�����X���ɑ��铖�ʂ̑�ɂ��Ă��܂Ƃ߁A�悤�₭��ɏ��o���܂����B���N�x�S���������̎����x���{�݂ɍ����x�����A�����Ƒ��ɖ����h�������J�݂���Ƃ��Ă��܂��B
�@�����̂ł������s�ł͓�\�O��ƂƂ��ɁA�A�J�ӗ~�̂���l�����������ԏh�������A�������x������H�㐶���Ҏ����x���Z���^�[���܂����ɐݒu���邱�Ƃ����߁A�挎���Ŏ��Ƃ��J�n����܂����B�_�ސ쌧���������������{���A���N�㌎�Ɍ��s�����A����c��ݒu���܂����B�Ƃ��낪�A�{���͂Ƃ����ƁA�[���ȎЉ���ƂȂ��Ă���z�[�����X���ɂ��Ď��Ԓ�������s���Ă��܂���B����̉��A�����̕����H�㐶����]�V�Ȃ�����Ă�����Ԃ͂���ȏ���u�ł��܂���B�ً}�ɑ���u����ׂ��ł��B��̍�Ƃ��Ď��̓�_���Ă��܂��B
�@���ɁA���Ƃ��ĕ�����蒲�����܂߂����Ԓ������s���A�l������闧�ꂩ��Z���̊m�ۂ�H���̒A�A�J���k��A�J�̏�̒A��ÃP�A�Ȃǂ̑����̉����ׂ��ł��B
�@���ɁA�z�[�����X���}�����Ă���w�i�����Z�N�ォ��̓K�����̖��ɂ�鐶���ی�s���̋ɒ[�Ȓ��߂������邱�Ƃ͖��炩�ł��B�����Ȃ͍��N�O���̎����̒S���҉�c�ł��A�u�Z���̗L���͏����ł͂Ȃ����ƁA�����\�͂͂����Ă����E�ɓw�͂��Ă���Εی�̑ΏۂƂȂ�v�Ɛ������Ă��܂��B���Ƃ��Ă����l�ȗ���Ő����ی�s���ɓ�����ƂƂ��ɁA�s�����ɑ��Đ����ی�\���͕K���t����悤�O�ꂷ�ׂ��ł���܂��B�܂��A�����ی�̓K���������߂��S��\�O���ʒm�͓P��悤���ɋ��߂�ׂ��ł��B
P.238�@�� ��㏻�q���N��������
���ɁA�䎿��Z�A�z�[�����X��Ɛ����ی�s���̏[���ɂ��Ă������\���グ�܂��B
�@�܂��A���Ԓ����Ƒ�ɂ��Ăł������܂����A�{���ɂ�����z�[�����X�̕��X�̎��Ԃɂ��܂��ẮA�S����v�s�s��ΏۂƂ��������ɂ��܂��ƁA�����\��N�\�����݁A��{�s�Z�\��l�A����s�Z�\�ܐl�ƂȂ��Ă���܂����A���S�̂ł̎����͔c������Ă���܂��Ƃ���A���Ԓ����ɂ��܂��ẮA����s�������W�@�ւƂ̘A�g��}��Ȃ��炻�̑̐����ɂ��Č������Ă܂��肽���Ƒ����܂��B
�@���݁A���ɂ����܂��ẮA�W�Ȓ��y�ъW�����̂ō\������z�[�����X���A����c�����܂Ƃ߂����ʂ̑Ή���Ɋ�Â��A�z�[�����X�����x�����ƂȂǂ𐄐i���Ă���܂��B���ɂ����܂��Ă��A�z�[�����X��̊�{�͎���̈ӎv�Ŏ������Đ����ł���悤�x�����邱�Ƃɂ���Ƃ̔F���̉��ɁA�A�J�̖��ɂ��܂��Ă̓n���[���[�N�ƘA�g����ƂƂ��ɁA�����̑��k��Z���A��ÂȂǂɂ��܂��ẮA�����ی�@�̊��p���܂ߌ䑊�k�ɑΉ��ł��܂��悤�����������ɑ��Ĉ��������������s���Ă܂��肽���Ƒ����܂��B
�@���ɁA�����ی�s���ɂ��Ăł������܂����A�����ی�@�͌��@�ŕۏႳ�ꂽ������������������̂ł���A�����납�炻�̏d�v����F�����A�@�̓K���ȉ^�p�ɓw�߂Ă���Ƃ���ł������܂��āA���{�@�ւł��镟���������ɑ��܂��ẮA�ی��K�v�Ƃ������̑��k�ɍۂ��A�Z���̗L����ғ��\�͂Ȃǂɂ��ĕ\�ʓI�ɂƂ炦�邱�ƂȂ��A���̍����̎��Ԃ��\���c��������ŁA�ی�̓K�p�ɂ��Č�������悤�������s���Ă���Ƃ���ł������܂��B�܂��A�ی�̐\���ɂ��܂��ẮA���x�̎�|���\���������A�\���ӎv�̂�����ɂ��܂��ẮA�\�������A���̏�ŕK�v�Ȓ����Ɋ�Â��Č��肷��悤�������Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@���ɁA�S��\�O���ʒm�ɂ��܂��ẮA�^�ɕی삪�K�v�ȕ��ɓK�ȕی삪�s����悤���Y������̊m�F�����Ȃǂɂ��Ď���������������Ă�������ł������܂��āA�ی��K�v�Ƃ�����̗�����\�����d���A�K���ɉ^�p���Ă܂���܂��̂ŁA�䗝�������肽���Ƒ����܂��B
�y�@�����P�P�N�@�@�Q���@����-02��26���|05���@�z
P.514�@�� ���\���ԁi�`�N���c���j
���ɁA�z�[�����X���ɂ��Ď��₵�܂��B
�@��{�s���ɂ́A��{�w���ӂ𒆐S�ɁA�����̕��s�҃f�b�L����������ɏZ�ݒ����Ă���z�[�����X���O�\�]��������ƌ����Ă��܂��B���ɁA��{�w�����̃A���V�F�O�̕��s�҃f�b�L���̊K�i�t�߂ɂ͏\�ܖ��߂����̃z�[�����X���W�c�ŐQ���܂肵�Ă��܂��B�i�{�[���A�ѕz�A�ߗށA�P�A�����p��̐����K���i���������ƕ��ׂĂ�����̂ŁA�܂��̌i�ς����j�Q���Ă��܂��B
�@���̏ꏊ�͑�{�w�����̉w���ɂ��邽�߁A�����吨�̐l���������Ă��āA�Ђキ�������Ă��܂��B�܂��A�����͓�K�̕��s�҃f�b�L�̍L��Œi�{�[����~���ĐQ����A�����Ɩق荞��ō����Ă��邽�߁A��x�݂��悤�Ƃ��鍂��ғ������ꏊ��D��ꂽ��ԂɂȂ��Ă��܂��B
�@�������A���̂܂܂̏�Ԃ������Ă����ƁA�s�������ɂ��Ȃ�̉e�����o�Ă�����̂ƗJ�����Ă��܂��B
�@�z�[�����X�́A���ꂼ�ꍡ���Ɏ������l�X�Ȏ������Ǝv���܂����A���l�߂�o�u������̋]���҂ł�����܂��B���́A�s���Ńz�[�����X���}�����Ă��邱�Ƃ��d�����āA���̓\����ɁA���Ɠ����s�A���l�s�A���s�A���É��s�A���s�Ńz�[�����X���A����c��ݒu���āA�z�[�����X��ɏ��o���܂����B���玩������ӎv�������Ȃ��z�[�����X�̎����x����͂قƂ�Ǎl����]�n���Ȃ��Ǝv���܂����A�Љ��艻���Ă��鍡���A���̂܂ܕ��u���Ă����킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA�l���I�ȗ���ɗ����āA����A������������Ă������������Ǝv���܂����A���̂��Ƃɂ��Ă̌������A�����J�����H�����y�ь��N���������ɂ��f�����܂��B
�������G�v�J�����H�����@�䎿��l�A�z�[�����X���ɂ��Ă̂����A���ɑ���䎿��ɂ�������\���グ�܂��B
�@������z�[�����X�̕��X�́A�l�X�Ȃ������œ��X���߂�����A�܂��A�����̖�������Ă�����̂Ǝv���A���̌ٗp�Ƃ������Ƃɂ��܂��ẮA�K�������A�J�ӗ~�����邩�ǂ����c������������������܂��B���݁A�����\�l�̌����E�ƈ��菊�ōs���Ă���܂��E�ƏЉ�ɂ��܂��ẮA�A�J�ӗ~�����������E�҂ɑ���A�E�����̎x���Ƃ��Ď��g��ł���Ƃ���ł������܂��āA�z�[�����X��ɂ��܂��ẮA���b�ɂ������܂����Ƃ���A���݁A���ɂ����܂��āA�z�[�����X���}�����Ă���܂������s����s�ȂǁA�܂̑�s�s�����̂ƍ��̊W�Ȓ��ɂ��܂��z�[�����X���A����c��ݒu���A�Ή��ɏ��o�����Ƃ���ł������܂��̂ŁA����A���̓������\���������Ă܂��肽���Ƒ����܂��B
�����������N���������@�䎿��l�A�z�[�����X���ɂ��Ă̂����A���ɑ���䎿��ɂ�������\���グ�܂��B
�@������H��Ő������Ă��邢����z�[�����X�ƌĂ��l�X�̖{���ɂ�������Ԃɂ��܂��ẮA�����̕��X���ړ����邱�Ƃ�����A���m�ɂ͔c������Ă��Ȃ��̂������ł������܂��B����܂ł��A�����Ɋւ��鑊�k�ɂ��܂��ẮA�������������ɂ����܂��ČX�ɑΉ����Ă��Ă���Ƃ����ł������܂����A�����̕��X�������Ă�����́A��������݂̂Ȃ炸�A��ÁA�ٗp�A�Z��ȂǕ��L������ɋy�ԂƂƂ��ɁA�����̌��������G������ɂ킽���Ă���܂��B���̂��߁A�z�[�����X���ւ̑�ɂ��܂��ẮA�����͂��ߓs���{���A�s�������ǂ̂悤�Ȗ�����S���Ή����Ă����̂��A���ɂ����Ă��A�W�����̂̋��͂Č������J�n���ꂽ�ƕ����Ă���܂��B
�@���Ƃ������܂��ẮA�����������̓����܂��܂��āA�s������W�@�ւƂ̘A�g��}��Ȃ���A���̑Ή��ɂ��Č������Ă܂��肽���Ƒ����܂��B