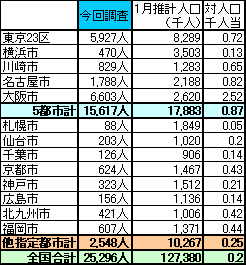
全国野宿生活者調査結果公表される
把握人数全国で25,296人(大阪府下7,752人)
大阪市内6,603人(市内人口千人に対して2.5人)
「ホームレスの自立の支援などに関する特別措置法」第14条の規定により、「ホームレスの自立支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、として、ホームレスの実態に関する全国調査が、1月から2月にかけて実施された。
調査は、①全市区町村において目視によるホームレスの数の調査 ②約2,000人を対象に面接による生活実態調査、の2つ。
数量把握の結果は、初めて日本全国(1都1道2府34県)で把握された(次ページに掲載)。
聞き取り調査は、2001(H13)年9月末野宿生活者確認数によって全国で2000名を目標に各都市に割り振られて実施された。釜ヶ崎支援機構は大阪市割り当ての内釜ヶ崎地区分について担当した。
割当数―東京23区400人・大阪市500人・名古屋市180人・川崎市180人・横浜市100人・京都市80人・神戸市60人・福岡市60人・広島市40人・北九州市40人・仙台市30人・千葉市20人・札幌市20人・堺市40人・豊橋市40人・さいたま市40人・浜松市40人・市川市40人・松山市20人・厚木市20人・尼崎市20人・八尾市20人・舟橋市20人。
今回調査は、大阪市内については目安にすぎないと考えるが、大阪市内は8,660人から6,603人と2,057人減少したことになっている。大阪市を除く府下では、逆に292人増加となっている。
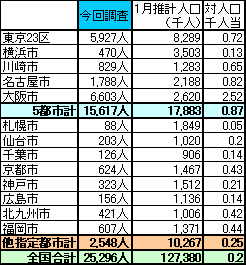
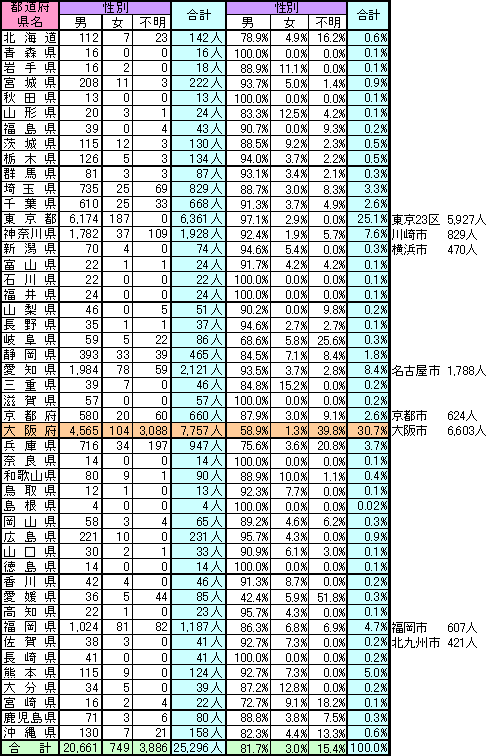
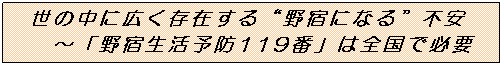
全国の聞き取り調査の「今回の野宿生活をするようになって、どの位経ちますか」の回答によれば、1年から3年未満が最も多く25.6%を占めている。1年未満を加えると56.4%にもおよぶ(右グラフ)。半年未満が18.4%ある。夜間宿所で今年3月におこなったアンケートでも、半年未満が18.3%で、奇しくも全国調査と似通った数字となっている。(ちなみに、平均年齢は55.9歳で全く同じ)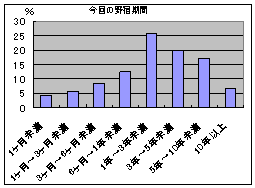
半年未満が2割近くもあるということは、野宿生活者が日々増加し続けていることを示すものである。全国でも、釜ヶ崎でも、同じ傾向を示している。このことは、野宿生活者への「自立支援」の対策だけでは充分ではなく、野宿生活に至る一歩手前での対策が必要であるという当たり前のことを裏付けている。
現に野宿を余儀なくされている人の側からではなく、野宿にいたるおそれを抱いている人の側から、一歩手前の対策としてどのようなことが必要かを探ろうとして、また、どのような助言が必要かを探ろうとして、釜ヶ崎支援機構は、連合大阪と協力して電話相談「野宿生活予防119番」を実施した(36件)。
相談者の中には、失業あるいは病気を原因として知人宅に同居している人が6人いたが、同居させてもらっている知人も失業し、行き先がなくなるという本当に「一歩手前」の人もいた。野宿生活1ヶ月の2人は雇用保険給付金の受給修了者だった。受給中の2人が、先行き不安で電話をかけてきた。高齢で自営業の維持が困難な老夫婦も不安を訴えた。
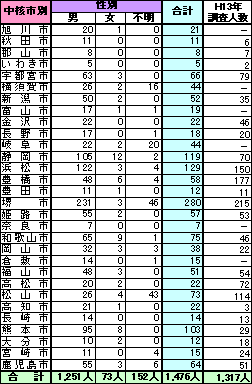
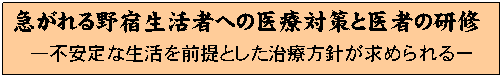
聞き取りの「野宿生活している間(長い方はここ1年以内)で次のような症状がありましたか。当てはまるものを幾つでも選んでください。」に対する回答が、右下の表。全く元気と思われるのは、3割程度と思われ、ほとんどは何らかの症状を経験しているか、今も感じている。
現在の体調を問うた問いに対して、身体の具合が悪いと答えているのは1,025名(47.7%)。その中で通院しているもの202人(19.7%)、売薬に頼るもの122人(11.9%)、何もしていないものは701人で68.4%を占めている。
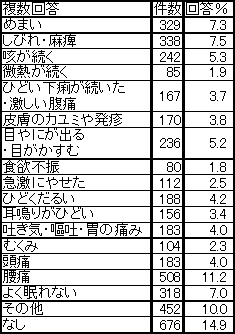
2000年の大阪市内行路病死者の死因等を研究したグループの成果により、野宿生活者の標準化死亡比は、総死因で3.56であることが明らかになっている。(安定した居所を確保して生活を送る人よりも野宿生活者の方が、3.56倍死亡確率が高いといえる。)
野宿生活者が医療にかかれる体制を早急に全国各地で確立する必要がある。
野宿生活者が医療のかかれる体制を確立する前提として、医療機関で働く人々に、野宿生活者のおかれている立場・生活について理解してもらう必要がある。
釜ヶ崎支援機構のつらい体験が、そのことを裏付けている。
3月7日、府下大津川河川敷で就労していた輪番労働者が体調不良を訴え、救急車で泉大津の病院に運ばれた。そのときすでに自分の力では立つことも歩くこともできない状態であった。
搬送先の病院で点滴を受けたが、医者の判断は、その病院での入院は不適当で、生活の場の近くの病院にかかるようにというものであった。釜ヶ崎に帰り、再び救急搬送、k病院に入院。11日に亡くなった。
第1次搬送病院の対応に疑念の残る経過であったので、担当医に事実確認におもむいて、以下の話を聞くことができた。
「立場上(病院長)、救急を担当することは年に1度か2度くらいしかなく、今回はたまたま私が担当する日だった。この病院の地域外の人の救急患者はそう多くなく、電車の中で気分が悪くなって運ばれてくる人があるくらい。そういう人達は、応急手当をすませれば、居住地の医療機関にすぐ移られる。当病院は急性期の病院で、平均入院期間も12日と短い。谷口さんも、なじみのある地域に帰って医療を受けるのがいいと考えた。そのつもりでその日の内に医者に行くように、念を押した。
しかし、その後、谷口さんが亡くなられたことを聞き、また、昨日の新聞やテレビなどで野宿をしている人が全国的に多いことを知り、これからも増え続けるだろうと考えたときに、そういった立場に置かれている人の背景や立場に考慮した治療を考える必要があったと反省している。今後は、救急を担当する内科医全員に、患者の社会的背景をも考慮に入れた治療方針を選択するよう伝える。
ただ、この病院は平均入院期間が短いので、転院が常にある。転院先の心配や退院後の患者さんの生活のことなどで、今後、釜ヶ崎支援機構として相談にのってもらえるとありがたい。」
課題は多く、大きく、重い。
命あるうちに…野宿から脱出できる施策を!
2003年2月3日朝、大テントがある中之島公園のばら園で1人の野宿生活者が亡くなっていました。ばら園入り口近く木立のなかに小屋がけをしておられましたが、亡くなるしばらく前は立ち上がる力もなくなっていたそうです。反失業連絡会の炊き出しが近くで行われています。隣に住む仲間が、「炊き出しを食べに行ったら?」と勧めていたそうですが…。日曜日の訪問活動で、お弁当を渡したこともあったそうです。でも、それだけで、追いつくものでもありません。
享年71歳。すでに福祉にかかれる年齢です。そうしなかったのには理由があるに違いありません。68歳になる隣人の方もこの事件をきっかけとして、「生活保護を受ける決心がついた」と言っておられました。「自活をしたい」という思いが、野宿のままでの孤独死につながってしまっている現実からも、行政・社会の側がバリアを外し、仕事と生活の保障制度づくりを行うことの重要性が浮き彫りにされているのではないでしょうか?
朝、晩2回、追悼を行いました(右写真)。
あの世でひもじい思いをすることがないように、丼に大盛りにした白飯と花を捧げました。(釜ヶ崎反失業連絡会)
